2010年02月18日
【取材】環境NPO法人H-imagine 松本英揮さん 後編
インタビュー後編。前編はこちら。
CCC:次に、H-imagineさんの活動資金面について教えていただけますか?
松本:宮崎県からの事業で市民ボランティアや環境学習などを行って予算をもらったり、個別に講演会を行う場合はその謝礼を頂いたりしています。しかし、最終的にボランティアでは社会は良くならないと思っています。最も福祉・政治・経済・教育・環境が充実している北ヨーロッパの国々ではボランティアは存在していません。社会が成熟するためには、どのような仕事をしてもキチンと対価をもらうことが必要です。お金でなくても、パンやお米などを頂いたりでもいいんです。日本人はすごく人がいいから、ただでボランティアしたら充実した気持ちにはなるけれど、その人はどこかで環境に悪い仕事をしてお金を稼がなきゃいけないかもしれません。だから良いことをしてお金が貰えるような社会にならなくてはいけないと考えています。NPOの考え方も、Nonprofit Organization(利益を出さない組織)ではなく、New public Organization(新しい公的組織)という考えが増えていますが、僕もそれが正しいと思っています。生活の中でなるべくお金を使わないということも大事です。自分で野菜やお米をつくれば、NPO活動で得たお金をまた活動に費やすことも出来ます。半分は畑仕事をやって、半分好きなことをやれば、いやな仕事は一切しなくて済むしね。
CCC:それでは、NPO活動にとっての障害などはありますか?
松本:障害は特にないね。障害をもたないようにはしています。最初に話したように、すごく変な方向に向かっている世の中をいい方向に変えていくためにつくったNPOだから、障害といえばそれが一番ですね。例えば、最近はうつ病の人が急増していますよね。これは1つの大きな社会現象で、経済がダメになり、環境がダメになると、次は人間の心にも影響がでるわけです。そういう人たちと向き合う時間がすごく増えています。障害ではないけど、現実的にすごくおかしな方向に行ってるのは確かです。
現実をキチンと把握して、薬に依存しないようにとか、逆に環境にいい生活をして、心もいい方向に変えていくというのが僕達の役割だと思っています。
CCC:なるほど。行政などに求める制度などはありますか?
松本:やっぱり今まで話した交通システムの改善・センター試験の廃止ですね。びっくりだよね、シンポジウムで「センター試験止めまーす!」なんて言い出したら(笑)僕達がセンター試験の元年になるけど、最初の年はえらい簡単でしたよ。最近はやっぱり難しくなってると思いますよ。
CCC:確かに難しかったです・・・これも実現可能なんですよね?
松本:うん、10年後にやる(断言)。
CCC:おおお。路面電車計画も、市長が変わられるので今から活動開始というわけですね。
松本:第1次計画で予算が約500億円と、たしかにお金もかかります。でも、宮崎県のレベルで考えたら500億円くらいの公共工事は少し前までたくさんありましたからね。僕も昔は建設会社を経営していたんですが、考え方次第では、公共投資のためにそのくらいのお金を使うことは決して高いものではないんです。
CCC:計画実現のために、住民の方々に対する説明などは?
松本:今までも県庁や宮崎市役所・市内の学校などで、DVDを300回以上上映してきました。国土交通省や企業にも持っていきました。そういう草の根で、宮崎市民にこういう可能性がある、街がこういう風に素敵になると伝えています。あと市議会議員の方もエコツアーにお連れして、宮崎市と同規模の街の役所でこの街がどうやって素敵になったかというレクチャーを受けてもらい、帰ってきてから宮崎市議会で提案してもらったりします。最初は反発もありましたが、徐々に理解はしてもらっています。
CCC:これからの活動も「草の根」で行っていくわけですね。
松本:そうですね。議員や市長候補の方たちを集めてシンポジウムを開いたり、住民と行政の両方からのサンドイッチでやっています。
CCC:質問は変わりますが、100カ国以上旅した中で、どの国が最も印象に残っていますか?
松本:印象ねぇ…日本(笑)。やっぱり宮崎ですね。外国に暮らすことも視野に入れて旅していたけど、宮崎以外には住めません。宮崎が1番。それに気づいたのが一番の収穫でした。
どの国に行こうか迷っている大学生にそれぞれ提案するんですが、男の子のよく提案するのがサハラ砂漠。砂漠っていうのはすごく生きやすいところなんです。サハラ砂漠の地下4mには井戸があって、女性たちが頭に重い水を乗せて運ぶんですけど、背筋をピンとのばして歩いてるでしょ。あとは羊飼いの子供がやってきたりとか、そういう人間の本来の生きていく姿を見たらものすごく安心するわけ。それを見てすごいなぁと思うし、自分もそういう人間本来の生き方がしたいなって思うし。それを見たときに、日本では経験できないなんだかはらにストーンと落ちるものがあるんですよ。それから、サハラ砂漠で日が沈む頃に子供がいる家に泊めてもらいます。子供がいると安全だし、子供が好きだから。そこでは一日の生活費が約100円で、その生活費をおいて、子供と遊んだり料理したりして、また次の村へ向かうんです。
そうやって世界中の人たちと寝食を共にしながら旅すると、宮崎のことがよくわかってきます。
CCC:逆に、今まで行ってない国でこれから行きたい国はありますか?
松本:行きたい国はないです。でも中国の西端にあるウルムチから上海まで自転車横断したいなってイメージはありますね。1ヵ月半ぐらいかかるかな。何でかっていうと、多分今年アメリカが潰れてドルが紙切れになって、世界の中心が中国に移行していくから。中国も変わりつつあるんですが、未だに多くの問題を抱えている国で、中国国内にうつ病患者が1億人いると言われています。
CCC:1億人!?
松本:そう。何故そんなに多いのかというと、子供のころからゲーム漬け・ケータイ漬けで、しかも親世代の貧しい生活のなかに突然現れたものだから尚更ハマっちゃって。そういうのが悪いって意識も日本人ほどないし。
上海の郊外都市で行われた企業誘致の経済セミナーに、環境関係で唯一呼ばれた際、うつ病の高校生と出会いました。その高校生のお母さんにも頼まれて、バスケットボールとか汗を流したりしましたけど、その子が今どうしてるかすごく気になりますよね。日本にいたら悪い情報しか入ってこないし、現実に悪いことがいっぱい起きてるんですけど、実際に中国全土を走ったときにまた違うものも見えてくるのかなぁと思いますね。
あとタイのチエンマイでエイズプロジェクトをやろうとしてます。5年前にアフリカでエイズプロジェクトを行ったときに、日本の米ぬかを使いました。タイも米食だし、アフリカでも半分くらいは米が食べられてます。米ぬかを使ったことで、体温があがり、免疫も6倍になりました。
社会が悪くなっているのも、1人1人の体調が悪いから。もう半病人みたいになってるでしょ?不健康な生活のなかで体温がすごく下がってるから、ガン細胞やエイズウイルスに侵されやすくなってるんです。体温を高めてあげれば治癒するというのが西アフリカで成功しました。
タイではエイズ孤児がすごく増えていて、そういう子たちにも米ぬかを使ってあげたいと思い、全国から200万円ほど寄付が集まって、もうすこしでできます。
納豆や味噌・豆腐など、日本の発酵食品が体に良いということはすごいなぁと思うけど、僕達はそれを知っているわけだから、それを使って世界の人たちに貢献できたらいいなと思います。
君達も体を温めてね。そうすれば万病は治るから
CCC:はい、心がけます!
松本:あとは沸いてきたイメージで「こんなことしたい」とか「この国にいきたい」とか決めてますね。楽しくないことは一切しないから。まぁ100歳までには残りの国全部に行きたいね(笑)
CCC:応援しています!今日は本当にありがとうございました!
松本:よかったらエコツアーも参加してね!
★インタビュー終わり★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
このあと、松本さんは自転車で高鍋西中学校へ向かって出発されました。パワフルすぎる!
松本さんはエコの達人としてニュースで紹介されたこともあり、ご自宅には発電用の風車も完備!
取材に伺う前は、路面電車計画と聞いて正直非現実なんじゃ…なんて思っていましたが、世界を見てきた松本さんはさすがに説得力が違いました。まさに「百聞は一見に如かず」を体現した方でした。本当にありがとうございました!
インタビュー 仮屋 井上
○基本情報
■団体名 環境NPO法人 H-imagine
■所在地 〒880-0032 宮崎市霧島4丁目106 複合施設 ESORA内
■ホームページ http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~e1122m/Himagine/
社会起業支援サミット2010 in 宮崎では、当日、こうした取材内容も冊子として
配布させていただきます。ぜひ皆様、ふるってご参加ください。
社会起業支援サミット2010 in 宮崎
2010年2月20日(土)10時〜17時 宮崎産業経営大学にて(参加無料)
※終了後には、交流会(参加費500円)も予定しております。
お申し込みは、こちらから。
メール jya-mane2@hotmail.co.jp
Fax 0985-51-0859でも受け付けしております。
CCC:次に、H-imagineさんの活動資金面について教えていただけますか?
松本:宮崎県からの事業で市民ボランティアや環境学習などを行って予算をもらったり、個別に講演会を行う場合はその謝礼を頂いたりしています。しかし、最終的にボランティアでは社会は良くならないと思っています。最も福祉・政治・経済・教育・環境が充実している北ヨーロッパの国々ではボランティアは存在していません。社会が成熟するためには、どのような仕事をしてもキチンと対価をもらうことが必要です。お金でなくても、パンやお米などを頂いたりでもいいんです。日本人はすごく人がいいから、ただでボランティアしたら充実した気持ちにはなるけれど、その人はどこかで環境に悪い仕事をしてお金を稼がなきゃいけないかもしれません。だから良いことをしてお金が貰えるような社会にならなくてはいけないと考えています。NPOの考え方も、Nonprofit Organization(利益を出さない組織)ではなく、New public Organization(新しい公的組織)という考えが増えていますが、僕もそれが正しいと思っています。生活の中でなるべくお金を使わないということも大事です。自分で野菜やお米をつくれば、NPO活動で得たお金をまた活動に費やすことも出来ます。半分は畑仕事をやって、半分好きなことをやれば、いやな仕事は一切しなくて済むしね。
CCC:それでは、NPO活動にとっての障害などはありますか?
松本:障害は特にないね。障害をもたないようにはしています。最初に話したように、すごく変な方向に向かっている世の中をいい方向に変えていくためにつくったNPOだから、障害といえばそれが一番ですね。例えば、最近はうつ病の人が急増していますよね。これは1つの大きな社会現象で、経済がダメになり、環境がダメになると、次は人間の心にも影響がでるわけです。そういう人たちと向き合う時間がすごく増えています。障害ではないけど、現実的にすごくおかしな方向に行ってるのは確かです。
現実をキチンと把握して、薬に依存しないようにとか、逆に環境にいい生活をして、心もいい方向に変えていくというのが僕達の役割だと思っています。
CCC:なるほど。行政などに求める制度などはありますか?
松本:やっぱり今まで話した交通システムの改善・センター試験の廃止ですね。びっくりだよね、シンポジウムで「センター試験止めまーす!」なんて言い出したら(笑)僕達がセンター試験の元年になるけど、最初の年はえらい簡単でしたよ。最近はやっぱり難しくなってると思いますよ。
CCC:確かに難しかったです・・・これも実現可能なんですよね?
松本:うん、10年後にやる(断言)。
CCC:おおお。路面電車計画も、市長が変わられるので今から活動開始というわけですね。
松本:第1次計画で予算が約500億円と、たしかにお金もかかります。でも、宮崎県のレベルで考えたら500億円くらいの公共工事は少し前までたくさんありましたからね。僕も昔は建設会社を経営していたんですが、考え方次第では、公共投資のためにそのくらいのお金を使うことは決して高いものではないんです。
CCC:計画実現のために、住民の方々に対する説明などは?
松本:今までも県庁や宮崎市役所・市内の学校などで、DVDを300回以上上映してきました。国土交通省や企業にも持っていきました。そういう草の根で、宮崎市民にこういう可能性がある、街がこういう風に素敵になると伝えています。あと市議会議員の方もエコツアーにお連れして、宮崎市と同規模の街の役所でこの街がどうやって素敵になったかというレクチャーを受けてもらい、帰ってきてから宮崎市議会で提案してもらったりします。最初は反発もありましたが、徐々に理解はしてもらっています。
CCC:これからの活動も「草の根」で行っていくわけですね。
松本:そうですね。議員や市長候補の方たちを集めてシンポジウムを開いたり、住民と行政の両方からのサンドイッチでやっています。
CCC:質問は変わりますが、100カ国以上旅した中で、どの国が最も印象に残っていますか?
松本:印象ねぇ…日本(笑)。やっぱり宮崎ですね。外国に暮らすことも視野に入れて旅していたけど、宮崎以外には住めません。宮崎が1番。それに気づいたのが一番の収穫でした。
どの国に行こうか迷っている大学生にそれぞれ提案するんですが、男の子のよく提案するのがサハラ砂漠。砂漠っていうのはすごく生きやすいところなんです。サハラ砂漠の地下4mには井戸があって、女性たちが頭に重い水を乗せて運ぶんですけど、背筋をピンとのばして歩いてるでしょ。あとは羊飼いの子供がやってきたりとか、そういう人間の本来の生きていく姿を見たらものすごく安心するわけ。それを見てすごいなぁと思うし、自分もそういう人間本来の生き方がしたいなって思うし。それを見たときに、日本では経験できないなんだかはらにストーンと落ちるものがあるんですよ。それから、サハラ砂漠で日が沈む頃に子供がいる家に泊めてもらいます。子供がいると安全だし、子供が好きだから。そこでは一日の生活費が約100円で、その生活費をおいて、子供と遊んだり料理したりして、また次の村へ向かうんです。
そうやって世界中の人たちと寝食を共にしながら旅すると、宮崎のことがよくわかってきます。
CCC:逆に、今まで行ってない国でこれから行きたい国はありますか?
松本:行きたい国はないです。でも中国の西端にあるウルムチから上海まで自転車横断したいなってイメージはありますね。1ヵ月半ぐらいかかるかな。何でかっていうと、多分今年アメリカが潰れてドルが紙切れになって、世界の中心が中国に移行していくから。中国も変わりつつあるんですが、未だに多くの問題を抱えている国で、中国国内にうつ病患者が1億人いると言われています。
CCC:1億人!?
松本:そう。何故そんなに多いのかというと、子供のころからゲーム漬け・ケータイ漬けで、しかも親世代の貧しい生活のなかに突然現れたものだから尚更ハマっちゃって。そういうのが悪いって意識も日本人ほどないし。
上海の郊外都市で行われた企業誘致の経済セミナーに、環境関係で唯一呼ばれた際、うつ病の高校生と出会いました。その高校生のお母さんにも頼まれて、バスケットボールとか汗を流したりしましたけど、その子が今どうしてるかすごく気になりますよね。日本にいたら悪い情報しか入ってこないし、現実に悪いことがいっぱい起きてるんですけど、実際に中国全土を走ったときにまた違うものも見えてくるのかなぁと思いますね。
あとタイのチエンマイでエイズプロジェクトをやろうとしてます。5年前にアフリカでエイズプロジェクトを行ったときに、日本の米ぬかを使いました。タイも米食だし、アフリカでも半分くらいは米が食べられてます。米ぬかを使ったことで、体温があがり、免疫も6倍になりました。
社会が悪くなっているのも、1人1人の体調が悪いから。もう半病人みたいになってるでしょ?不健康な生活のなかで体温がすごく下がってるから、ガン細胞やエイズウイルスに侵されやすくなってるんです。体温を高めてあげれば治癒するというのが西アフリカで成功しました。
タイではエイズ孤児がすごく増えていて、そういう子たちにも米ぬかを使ってあげたいと思い、全国から200万円ほど寄付が集まって、もうすこしでできます。
納豆や味噌・豆腐など、日本の発酵食品が体に良いということはすごいなぁと思うけど、僕達はそれを知っているわけだから、それを使って世界の人たちに貢献できたらいいなと思います。
君達も体を温めてね。そうすれば万病は治るから
CCC:はい、心がけます!
松本:あとは沸いてきたイメージで「こんなことしたい」とか「この国にいきたい」とか決めてますね。楽しくないことは一切しないから。まぁ100歳までには残りの国全部に行きたいね(笑)
CCC:応援しています!今日は本当にありがとうございました!
松本:よかったらエコツアーも参加してね!
★インタビュー終わり★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
このあと、松本さんは自転車で高鍋西中学校へ向かって出発されました。パワフルすぎる!
松本さんはエコの達人としてニュースで紹介されたこともあり、ご自宅には発電用の風車も完備!
取材に伺う前は、路面電車計画と聞いて正直非現実なんじゃ…なんて思っていましたが、世界を見てきた松本さんはさすがに説得力が違いました。まさに「百聞は一見に如かず」を体現した方でした。本当にありがとうございました!
インタビュー 仮屋 井上
○基本情報
■団体名 環境NPO法人 H-imagine
■所在地 〒880-0032 宮崎市霧島4丁目106 複合施設 ESORA内
■ホームページ http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~e1122m/Himagine/
社会起業支援サミット2010 in 宮崎では、当日、こうした取材内容も冊子として
配布させていただきます。ぜひ皆様、ふるってご参加ください。
社会起業支援サミット2010 in 宮崎
2010年2月20日(土)10時〜17時 宮崎産業経営大学にて(参加無料)
※終了後には、交流会(参加費500円)も予定しております。
お申し込みは、こちらから。
メール jya-mane2@hotmail.co.jp
Fax 0985-51-0859でも受け付けしております。
2010年02月15日
【取材】NPO法人ドロップインセンターさま (後編)
インタビューの前編はこちら。
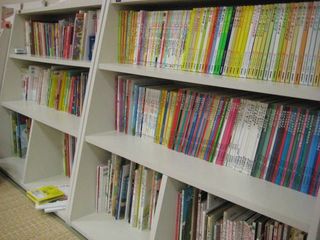
(写真:たくさんの絵本が並ぶ)
CCC (一同悩む)例えば、企業と利用者の折半とか、そういった形での展開ができるといいかもしれませんね。企業も社会の一員として、子育てを支援する社会だったらいいのでしょうね。(一同うなづく)
さて、時間も迫ってきましたので、皆さまに2点お伺いしたいのですが、1つは、障害になっていることは何ですか?ということです。もう1つは、こんな制度があったらいいなと思うことは何ですか?ということです。
黒田 障害になっていることというか、課題なのですが、この活動で食べていける人を出さなくてはいけない、ということです。実は、今ここで働いている方のほとんどが、ご家庭に稼ぎ頭がいて、働いているという方です。正社員は5人ですが、市の嘱託社員と同じ給料です。スキルを持っているにもかかわらず、です。ですから、これを「職業」にしたいと思っています。
原田 そうなんですよね。年末に年越し派遣村というのが話題になりましたが、パートや派遣社員というのは、ずいぶん昔から女性の中にはいましたし、女性はそういう立場の人が多かったんです。男の人がパートや派遣になったとたん、国は動き出しました。そうではなくて、何か根本的な発想の転換が必要だと思います。
また、ビジネス化できない部分があれば、それはやっぱりみんながお金を出し合って活動していかなくてはいけないと思います。税金の使い方についても、声を出していくことが必要だろうと思います。
それから、もう1つ、今の活動に関わってくださる方は、だいたい子育てが終わった方が中心となっています。もっと早く関わりたかった、という方が大半です。ですから、若いお母さんたち、子育て真っ最中のお母さんたちが関わりやすい仕組みを作りたいと思います。

(写真:こどもらんどのおもちゃの数々。かつては誰しも子どもだった・・・)
黒田 あったらいいなと思う制度は、商店街の空き店舗を市民活動に活用できるような制度が欲しいということです。今、中心市街地の空き店舗はたくさんあります。一方で、市民活動をされている方で拠点が欲しい方はたくさんいます。ですから、その両方をマッチングする制度を創ってほしいということです。もちろん、拠点づくりにはお金がかかりますから、その辺りの補助金も欲しいところですが。
原田 私は、あったらいいなという制度というのではなくて私の夢なんですけれど、いくつかあります。1つは、共感の根っこ(ルーツオブエンパシー)という事業をしたいです。これもカナダで開発された教育プログラムですが、1つのクラスに幼児〜中学生、赤ちゃんと親が、4ヶ月〜5ヶ月間、週1回顔を合わせます。赤ちゃんの成長を通して、みんなが学んでいくというものです。
それから、もう1つは、ファシリテーター1万人計画、です。人と人とがつながっていくためには、その人間関係を構築していく力が必要だと思います。人間力を向上させていくことで、それぞれの人の能力が高まるような講座をしたいと思っています。
やっぱり、仕事も、子育ても、自分のこともできる社会、子どもを産むことが不利にならない社会にしていければなと思っています。
藤崎 私は見える場所で見える支援をしていきたいと思います。お母さんにとって、いつでも行ける、と思えることが大きな力になると思います。そんな場所を増やしていきたいと思います。

インタビュー 吉池、福原
♪゚゚インタビュー ここまで+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚
インタビュー後、カリーノ8階ガガエイトのこどもらんど・中央東地域子育てセンターさんで、
1歳半くらいのお子さんたちと遊ばせていただきました。
子どもの笑い声をいやだと思う人はいない、そのように語ってくださった原田さんの言葉が
とても印象的で、また、私たちも同じ女性として、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
○基本情報
■団体名 NPO法人ドロップインセンター
■所在地 宮崎市旭2丁目1−5総研ビル2階
■ホームページ http://www.drop-in.or.jp/
○あわせて読みたい
・街が元気だネット http://www.machi-gennki.net/npo-report/dropin/index.html
・WAM長寿・子育て・障害者基金事業 「子育支援セミナー」活動報告
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/kikinjigyou/main_07_05_3.html
・NPOレポート http://blog.livedoor.jp/miyazaki_machi/archives/50491490.html
・Nobody’s Perfect Japan http://homepage3.nifty.com/NP-Japan/
・ルーツ・オブ・エンパシー「家族を聖域にしてはいけない」 http://blog.katei-x.net/blog/2008/08/000610.html
社会起業支援サミット2010 in 宮崎では、当日、こうした取材内容も冊子として
配布させていただきます。ぜひ皆様、ふるってご参加ください。
社会起業支援サミット2010 in 宮崎
2010年2月20日(土)10時〜17時 宮崎産業経営大学にて(参加無料)
※終了後には、交流会(参加費500円)も予定しております。
お申し込みは、こちらから。
メール jya-mane2@hotmail.co.jp
Fax 0985-51-0859でも受け付けしております。
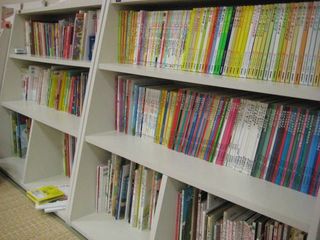
(写真:たくさんの絵本が並ぶ)
CCC (一同悩む)例えば、企業と利用者の折半とか、そういった形での展開ができるといいかもしれませんね。企業も社会の一員として、子育てを支援する社会だったらいいのでしょうね。(一同うなづく)
さて、時間も迫ってきましたので、皆さまに2点お伺いしたいのですが、1つは、障害になっていることは何ですか?ということです。もう1つは、こんな制度があったらいいなと思うことは何ですか?ということです。
黒田 障害になっていることというか、課題なのですが、この活動で食べていける人を出さなくてはいけない、ということです。実は、今ここで働いている方のほとんどが、ご家庭に稼ぎ頭がいて、働いているという方です。正社員は5人ですが、市の嘱託社員と同じ給料です。スキルを持っているにもかかわらず、です。ですから、これを「職業」にしたいと思っています。
原田 そうなんですよね。年末に年越し派遣村というのが話題になりましたが、パートや派遣社員というのは、ずいぶん昔から女性の中にはいましたし、女性はそういう立場の人が多かったんです。男の人がパートや派遣になったとたん、国は動き出しました。そうではなくて、何か根本的な発想の転換が必要だと思います。
また、ビジネス化できない部分があれば、それはやっぱりみんながお金を出し合って活動していかなくてはいけないと思います。税金の使い方についても、声を出していくことが必要だろうと思います。
それから、もう1つ、今の活動に関わってくださる方は、だいたい子育てが終わった方が中心となっています。もっと早く関わりたかった、という方が大半です。ですから、若いお母さんたち、子育て真っ最中のお母さんたちが関わりやすい仕組みを作りたいと思います。

(写真:こどもらんどのおもちゃの数々。かつては誰しも子どもだった・・・)
黒田 あったらいいなと思う制度は、商店街の空き店舗を市民活動に活用できるような制度が欲しいということです。今、中心市街地の空き店舗はたくさんあります。一方で、市民活動をされている方で拠点が欲しい方はたくさんいます。ですから、その両方をマッチングする制度を創ってほしいということです。もちろん、拠点づくりにはお金がかかりますから、その辺りの補助金も欲しいところですが。
原田 私は、あったらいいなという制度というのではなくて私の夢なんですけれど、いくつかあります。1つは、共感の根っこ(ルーツオブエンパシー)という事業をしたいです。これもカナダで開発された教育プログラムですが、1つのクラスに幼児〜中学生、赤ちゃんと親が、4ヶ月〜5ヶ月間、週1回顔を合わせます。赤ちゃんの成長を通して、みんなが学んでいくというものです。
それから、もう1つは、ファシリテーター1万人計画、です。人と人とがつながっていくためには、その人間関係を構築していく力が必要だと思います。人間力を向上させていくことで、それぞれの人の能力が高まるような講座をしたいと思っています。
やっぱり、仕事も、子育ても、自分のこともできる社会、子どもを産むことが不利にならない社会にしていければなと思っています。
藤崎 私は見える場所で見える支援をしていきたいと思います。お母さんにとって、いつでも行ける、と思えることが大きな力になると思います。そんな場所を増やしていきたいと思います。

インタビュー 吉池、福原
♪゚゚インタビュー ここまで+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚゚+.・.。*゚♪゚
インタビュー後、カリーノ8階ガガエイトのこどもらんど・中央東地域子育てセンターさんで、
1歳半くらいのお子さんたちと遊ばせていただきました。
子どもの笑い声をいやだと思う人はいない、そのように語ってくださった原田さんの言葉が
とても印象的で、また、私たちも同じ女性として、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
○基本情報
■団体名 NPO法人ドロップインセンター
■所在地 宮崎市旭2丁目1−5総研ビル2階
■ホームページ http://www.drop-in.or.jp/
○あわせて読みたい
・街が元気だネット http://www.machi-gennki.net/npo-report/dropin/index.html
・WAM長寿・子育て・障害者基金事業 「子育支援セミナー」活動報告
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/kikinjigyou/main_07_05_3.html
・NPOレポート http://blog.livedoor.jp/miyazaki_machi/archives/50491490.html
・Nobody’s Perfect Japan http://homepage3.nifty.com/NP-Japan/
・ルーツ・オブ・エンパシー「家族を聖域にしてはいけない」 http://blog.katei-x.net/blog/2008/08/000610.html
社会起業支援サミット2010 in 宮崎では、当日、こうした取材内容も冊子として
配布させていただきます。ぜひ皆様、ふるってご参加ください。
社会起業支援サミット2010 in 宮崎
2010年2月20日(土)10時〜17時 宮崎産業経営大学にて(参加無料)
※終了後には、交流会(参加費500円)も予定しております。
お申し込みは、こちらから。
メール jya-mane2@hotmail.co.jp
Fax 0985-51-0859でも受け付けしております。
2010年02月15日
【取材】NPO法人宮崎文化本舗 石田達也さん (後編)
インタビューの前編は、こちらへ
CCC なるほど。若い人にもチャンスがあるわけですね。また、宮崎文化本舗さんでは、サイトでNPOのネットワークづくりをされているとも拝見しました。このネットワーク作りの方法についても教えていただけますか?
石田 ネットワークという言葉をnet + work だと考えています。ネットは繋がること、そしてワークは動くこと・仕事をすること、だと考えます。つまり、ともに汗をかいてするということだろうと。例えば、何かの実行委員会をやるとします。そうすると、いろんな人がいろんな形で関わってきますが、誰が責任をとるのか、という話になってきます。そこをコーディネートするのが、私たちということになります。つなぎ役ともいうのでしょうか。そうすると、うまくいくところもあれば、そうでないところもある。実行委員会とは言っても、結局は、やるかやらないか、の世界だと思います。やる、と決めた人には応援してくれる人がつくし、いい加減だとまったく人はつかないということです。
CCC なるほど。人の生き方にも繋がる話ですね。それでは、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、今の活動で障害になっていることは何ですかということです。もう1つは、こういう制度があったらいいなということはありますか?ということです。
石田 障害になっていること。(うーん。としばらく考えられて)小さいことはいっぱいあるけれど、大きな意味ではありません。NPOもソーシャルビジネスも、コミュニティビジネスも、読み方が変わっただけで、みんな同じことなんですよね。そういう呼び方の違いの意味を見いだせないでいますが、本当に必要な言葉なんでしょうか。私たちは、今のNPOの形でうまくまわっていると思います。強いて言えば、みんなが納得した形で動かないといけないので、NPO法人とボランティアの合意形成に少し時間がかかる、ということでしょうか。
制度については、選挙制度を変える、ということです。
CCC えええ(一同驚愕)!
石田 (苦笑)今の議会をみていると、一度がらがらしないともう立ち行かない状態になっていますよね。世の中よくするためには、それが一番かと。今の税制もおかしいと思います。寄付という文化がない日本で、NPOは寄付のための税制をとっている。そして、税金は責任を持たない政府が集め、補助金や助成金など成果が見えないことにお金を出しています。そうではなくて、もっと市民が自らの意思で投資できる仕組みがあればいいなと思います。国は、地域の人の顔が見える仕組み、みんなで支えていこうとする仕組みをとる必要があると思います。

インタビュー 井上、吉池
★インタビュー ここまで★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
ご多忙のなか、快く取材に応じてくださった石田さん。本当にありがとうございました。
また、なかなか来場者が集まらないことを相談させていただき、いくつか対策を教えていただきました。
本当にありがとうございました。
スタッフ井上は、個人的に7月に開催される仮面ライダー展を楽しみにしております。
○基本情報
■団体名 NPO法人宮崎文化本舗
■所在地 宮崎市橘通東3丁目1番11号アゲインビル2F
■ホームページ http://www.bunkahonpo.or.jp/
○あわせて読みたい
・特集NPOレポート http://www.machi-gennki.net/npo-report/bunka/index.html
・ヒトミテ(前編) http://hitomite.jp/2009/08/20090827miyazaki.html
・ヒトミテ(後編)http://hitomite.jp/2009/09/20090903miyazaki.html
・ドリームゲートhttp://case.dreamgate.gr.jp/topics_detail7/id=240
・ソーシャルビジネスネット http://www.socialbusiness.jp/case/000115.html
・カンパンフィールズ http://canpan.info/open/dantai/00002764/dantai_detail.html
・経済産業省(PDF) http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/data55sen/p050_051.pdf
石田さんのお話が直接聞ける社会起業支援サミット2010 in 宮崎への
お申し込みはこちらから。
CCC なるほど。若い人にもチャンスがあるわけですね。また、宮崎文化本舗さんでは、サイトでNPOのネットワークづくりをされているとも拝見しました。このネットワーク作りの方法についても教えていただけますか?
石田 ネットワークという言葉をnet + work だと考えています。ネットは繋がること、そしてワークは動くこと・仕事をすること、だと考えます。つまり、ともに汗をかいてするということだろうと。例えば、何かの実行委員会をやるとします。そうすると、いろんな人がいろんな形で関わってきますが、誰が責任をとるのか、という話になってきます。そこをコーディネートするのが、私たちということになります。つなぎ役ともいうのでしょうか。そうすると、うまくいくところもあれば、そうでないところもある。実行委員会とは言っても、結局は、やるかやらないか、の世界だと思います。やる、と決めた人には応援してくれる人がつくし、いい加減だとまったく人はつかないということです。
CCC なるほど。人の生き方にも繋がる話ですね。それでは、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、今の活動で障害になっていることは何ですかということです。もう1つは、こういう制度があったらいいなということはありますか?ということです。
石田 障害になっていること。(うーん。としばらく考えられて)小さいことはいっぱいあるけれど、大きな意味ではありません。NPOもソーシャルビジネスも、コミュニティビジネスも、読み方が変わっただけで、みんな同じことなんですよね。そういう呼び方の違いの意味を見いだせないでいますが、本当に必要な言葉なんでしょうか。私たちは、今のNPOの形でうまくまわっていると思います。強いて言えば、みんなが納得した形で動かないといけないので、NPO法人とボランティアの合意形成に少し時間がかかる、ということでしょうか。
制度については、選挙制度を変える、ということです。
CCC えええ(一同驚愕)!
石田 (苦笑)今の議会をみていると、一度がらがらしないともう立ち行かない状態になっていますよね。世の中よくするためには、それが一番かと。今の税制もおかしいと思います。寄付という文化がない日本で、NPOは寄付のための税制をとっている。そして、税金は責任を持たない政府が集め、補助金や助成金など成果が見えないことにお金を出しています。そうではなくて、もっと市民が自らの意思で投資できる仕組みがあればいいなと思います。国は、地域の人の顔が見える仕組み、みんなで支えていこうとする仕組みをとる必要があると思います。

インタビュー 井上、吉池
★インタビュー ここまで★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
ご多忙のなか、快く取材に応じてくださった石田さん。本当にありがとうございました。
また、なかなか来場者が集まらないことを相談させていただき、いくつか対策を教えていただきました。
本当にありがとうございました。
スタッフ井上は、個人的に7月に開催される仮面ライダー展を楽しみにしております。
○基本情報
■団体名 NPO法人宮崎文化本舗
■所在地 宮崎市橘通東3丁目1番11号アゲインビル2F
■ホームページ http://www.bunkahonpo.or.jp/
○あわせて読みたい
・特集NPOレポート http://www.machi-gennki.net/npo-report/bunka/index.html
・ヒトミテ(前編) http://hitomite.jp/2009/08/20090827miyazaki.html
・ヒトミテ(後編)http://hitomite.jp/2009/09/20090903miyazaki.html
・ドリームゲートhttp://case.dreamgate.gr.jp/topics_detail7/id=240
・ソーシャルビジネスネット http://www.socialbusiness.jp/case/000115.html
・カンパンフィールズ http://canpan.info/open/dantai/00002764/dantai_detail.html
・経済産業省(PDF) http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/data55sen/p050_051.pdf
石田さんのお話が直接聞ける社会起業支援サミット2010 in 宮崎への
お申し込みはこちらから。
2010年02月15日
【取材】合同会社らくがきART 佐藤健郎さん 後編
インタビュー前編はこちら。

(写真:宮崎市小松の健康支援館はらくがきアートの常設展示場となっている)
CCC なるほど。とても深いお話ですね。
さて、次に宮崎での活動予定について教えてください。
佐藤 何もかもがこれからなのですが、まず宮崎で始めたいことは、らくがきアート教室(体験教室)です。これは僕が大分でやってきたノウハウに基づいてやりたいと思っています。大分(大分カルチャー学院)では5名の子どもさんがいました。また、体験教室(ワークショップ)には15名〜20名の参加がありました。どのようなことをやっていたかというと、まず子どもさんに「浜辺に行って、きれいとか、かっこいいと思うもの、面白いと思うものを10個拾ってこよう」という宿題を与えます。集まってきた材料を組み合わせて、アート作品を創ります。もちろん、僕は先生ですが、僕も同じことをします。子どもと同じことをして、自由に話をしながら、子どものアート制作の背中をおしていきます。言葉ではなくて、自分もやってみせながら伝えるわけです。最後に、みんなで発表を行います。発表時には、お迎えのお母さんやお父さんにも一緒にいていただきます。そして、お母さんやお父さんや僕といった大人が、子どもに質問するわけです。「なんでそれを創ろうと思ったの?」とか、「その絵は何?」とかです。5歳、8歳の子が一生懸命説明するのですが、ここで重要なのは、自分がやっていることを自分で伝えることができる、ということなんです。自分のやっていることを自分の手で表現し、自分の口で表現する、プレゼン力を磨く教室です。だから、通常のアート教室とはずいぶん違いますね。
CCC 子どもさんの様子はいかがですか?
佐藤 最初は無口で始めるのですが、どうしても途中で飽きて、走り回ったり、他の子の邪魔をしたりするわけです。ここで、僕が口を挟むのですが、僕は今、こういうことをやっている、製作がまだ終わっていないし、終わるためにはこの空白の空間はどうするつもりなの?などと言います。決して、騒ぐなとは言いません。教室は90分間ですが、90分内にきちんと作品として完成させるための手伝いをします。もちろん、やり遂げられないことが多いのですが、時間をコントロールするということも合わせて教えたいと思っています。
CCC とても面白い教室だと思います。今挙げてくださった教室事業のほかに、どういったものを収益事業として考えられていますか?
佐藤 他に4つの柱があります。1つは、そもそもの収益モデルで、子どもさんのらくがきをアート作品化し、それをファインアート(絵)やTシャツ、マグカップなどの製品にして販売するというものです。2つめは、まちおこし支援事業です。宮崎のコミュニティシンクタンクである有限会社サン・グロウ様と組ませていただいて、中山間地域のまちおこしをしようとしています。具体的には、農産物の加工品などをパッケージ化するにあたって、らくがきARTを活用していただこうとしています。まちの人の手による、まちのブランドづくりのお手伝いをしているわけです。3つめは、国際支援です。現在、いくつかの団体様にお声かけさせていただいています。神戸女子大の先生にもご協力いただき、NPOやNGOとの連携を産学恊働で進めているところです。4つめは、障害者(児)施設の方々にらくがきを描いていただき、それを利用したアート製品を作り、カレンダーを創ったり、施設の販売品のパッケージに使ったりして、その収益の一部を施設に還元していくというものです。今まで、生活学校(宇佐)様などで行わせていただいています。
CCC なるほど。らくがきARTさんはいろんな場面で活用可能だということですね。では、最後に、2つのお尋ねをしたいと思います。1つは現在の活動にあたって障害となっていることを教えていただきたいということです。もう1つは、あったらいいなという制度を教えてください。
佐藤 まず障害は、お金がないことです(苦笑)。今、会社組織にしたことで、アート作品化したときの収益の分配を、子どもさん20%、芸術家30%、会社50%としています。会社は50%の分配ですから、正直、大金持ちにはなりません。でも、僕はそれでいいと思っています。志を持ちつつ、事業を行っていくのが社会起業家だと思っていますから。
次に、あったらいいなという制度は、3つ有ります。1つめは、社会起業家に対する資金面での支援が欲しいということです。2つめは、人と人とのマッチング制度があったらいいなと思います。先ほども申しましたように、らくがきARTは活用する人がいてこそ、の会社です。アートを商品化する人、活用してまちおこし、福祉施設の運営に使いたい人、商品を買いたい人、そんな人たちをマッチングしていく制度が欲しいです。3つめは、社員を雇う場合の優遇措置です。NPO法人は特別な形態として設立され、税制面等の優遇措置がありますが、合同会社は普通の法人と同じ形態だと見られます。やっていることによらず、です。それでも僕たちが合同会社にこだわるのは、会社は存続することを使命としており、僕たちも存続することを使命としているからです。NPOは単年度ごとの会計で、利益を持ち越すことができません。企業は成長することが必要ですから、NPOのような会計で、収支0とすることは事業を行うための納得がいきません。また、奨学金は小さい頃から18歳までのお金を扱うということになりますから、絶対つぶすわけにはいかないんです。だから、企業形態にかかわらず、やっている活動(実態)で支援する仕組みができればと思います。

(写真:佐藤さんとCCC宮崎 井上、吉池)
★インタビュー終わり★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
当日は、常設展示場である健康支援館様に伺いました。
実際に絵を見てみると、百聞は一見にしかずということがよくわかります。
子どもさんのらくがきがアート作品化し、製品化することで、
子どものことを大人が意識する瞬間が増えること、
それが世界平和に繋がることを伺い、一同感動しながら帰路につきました。
お忙しいなか、本当にありがとうございました。
インタビュー 井上、吉池
○基本情報
■団体名 合同会社らくがきART
■所在地 東京都渋谷区元代々木町10−5 (近々神戸市に本社移転予定)
宮崎事務所 宮崎郡清武町大字加納
■ホームページ http://www.rakugakiart.jp/
○合わせて読みたい
■スタッフブログ http://shirokuma.hama1.jp/
佐藤さんのお話が直接聞ける社会起業支援サミット2010 in 宮崎への
お申し込みはこちらから。

(写真:宮崎市小松の健康支援館はらくがきアートの常設展示場となっている)
CCC なるほど。とても深いお話ですね。
さて、次に宮崎での活動予定について教えてください。
佐藤 何もかもがこれからなのですが、まず宮崎で始めたいことは、らくがきアート教室(体験教室)です。これは僕が大分でやってきたノウハウに基づいてやりたいと思っています。大分(大分カルチャー学院)では5名の子どもさんがいました。また、体験教室(ワークショップ)には15名〜20名の参加がありました。どのようなことをやっていたかというと、まず子どもさんに「浜辺に行って、きれいとか、かっこいいと思うもの、面白いと思うものを10個拾ってこよう」という宿題を与えます。集まってきた材料を組み合わせて、アート作品を創ります。もちろん、僕は先生ですが、僕も同じことをします。子どもと同じことをして、自由に話をしながら、子どものアート制作の背中をおしていきます。言葉ではなくて、自分もやってみせながら伝えるわけです。最後に、みんなで発表を行います。発表時には、お迎えのお母さんやお父さんにも一緒にいていただきます。そして、お母さんやお父さんや僕といった大人が、子どもに質問するわけです。「なんでそれを創ろうと思ったの?」とか、「その絵は何?」とかです。5歳、8歳の子が一生懸命説明するのですが、ここで重要なのは、自分がやっていることを自分で伝えることができる、ということなんです。自分のやっていることを自分の手で表現し、自分の口で表現する、プレゼン力を磨く教室です。だから、通常のアート教室とはずいぶん違いますね。
CCC 子どもさんの様子はいかがですか?
佐藤 最初は無口で始めるのですが、どうしても途中で飽きて、走り回ったり、他の子の邪魔をしたりするわけです。ここで、僕が口を挟むのですが、僕は今、こういうことをやっている、製作がまだ終わっていないし、終わるためにはこの空白の空間はどうするつもりなの?などと言います。決して、騒ぐなとは言いません。教室は90分間ですが、90分内にきちんと作品として完成させるための手伝いをします。もちろん、やり遂げられないことが多いのですが、時間をコントロールするということも合わせて教えたいと思っています。
CCC とても面白い教室だと思います。今挙げてくださった教室事業のほかに、どういったものを収益事業として考えられていますか?
佐藤 他に4つの柱があります。1つは、そもそもの収益モデルで、子どもさんのらくがきをアート作品化し、それをファインアート(絵)やTシャツ、マグカップなどの製品にして販売するというものです。2つめは、まちおこし支援事業です。宮崎のコミュニティシンクタンクである有限会社サン・グロウ様と組ませていただいて、中山間地域のまちおこしをしようとしています。具体的には、農産物の加工品などをパッケージ化するにあたって、らくがきARTを活用していただこうとしています。まちの人の手による、まちのブランドづくりのお手伝いをしているわけです。3つめは、国際支援です。現在、いくつかの団体様にお声かけさせていただいています。神戸女子大の先生にもご協力いただき、NPOやNGOとの連携を産学恊働で進めているところです。4つめは、障害者(児)施設の方々にらくがきを描いていただき、それを利用したアート製品を作り、カレンダーを創ったり、施設の販売品のパッケージに使ったりして、その収益の一部を施設に還元していくというものです。今まで、生活学校(宇佐)様などで行わせていただいています。
CCC なるほど。らくがきARTさんはいろんな場面で活用可能だということですね。では、最後に、2つのお尋ねをしたいと思います。1つは現在の活動にあたって障害となっていることを教えていただきたいということです。もう1つは、あったらいいなという制度を教えてください。
佐藤 まず障害は、お金がないことです(苦笑)。今、会社組織にしたことで、アート作品化したときの収益の分配を、子どもさん20%、芸術家30%、会社50%としています。会社は50%の分配ですから、正直、大金持ちにはなりません。でも、僕はそれでいいと思っています。志を持ちつつ、事業を行っていくのが社会起業家だと思っていますから。
次に、あったらいいなという制度は、3つ有ります。1つめは、社会起業家に対する資金面での支援が欲しいということです。2つめは、人と人とのマッチング制度があったらいいなと思います。先ほども申しましたように、らくがきARTは活用する人がいてこそ、の会社です。アートを商品化する人、活用してまちおこし、福祉施設の運営に使いたい人、商品を買いたい人、そんな人たちをマッチングしていく制度が欲しいです。3つめは、社員を雇う場合の優遇措置です。NPO法人は特別な形態として設立され、税制面等の優遇措置がありますが、合同会社は普通の法人と同じ形態だと見られます。やっていることによらず、です。それでも僕たちが合同会社にこだわるのは、会社は存続することを使命としており、僕たちも存続することを使命としているからです。NPOは単年度ごとの会計で、利益を持ち越すことができません。企業は成長することが必要ですから、NPOのような会計で、収支0とすることは事業を行うための納得がいきません。また、奨学金は小さい頃から18歳までのお金を扱うということになりますから、絶対つぶすわけにはいかないんです。だから、企業形態にかかわらず、やっている活動(実態)で支援する仕組みができればと思います。

(写真:佐藤さんとCCC宮崎 井上、吉池)
★インタビュー終わり★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
当日は、常設展示場である健康支援館様に伺いました。
実際に絵を見てみると、百聞は一見にしかずということがよくわかります。
子どもさんのらくがきがアート作品化し、製品化することで、
子どものことを大人が意識する瞬間が増えること、
それが世界平和に繋がることを伺い、一同感動しながら帰路につきました。
お忙しいなか、本当にありがとうございました。
インタビュー 井上、吉池
○基本情報
■団体名 合同会社らくがきART
■所在地 東京都渋谷区元代々木町10−5 (近々神戸市に本社移転予定)
宮崎事務所 宮崎郡清武町大字加納
■ホームページ http://www.rakugakiart.jp/
○合わせて読みたい
■スタッフブログ http://shirokuma.hama1.jp/
佐藤さんのお話が直接聞ける社会起業支援サミット2010 in 宮崎への
お申し込みはこちらから。
2010年02月12日
【取材】環境NPO法人H-imagine代表 松本英揮さん
本日は環境NPO法人H-imagine(ひまじん)さまに取材に伺いました。
インタビューにお答え下さったのは代表理事である“チャリで世界を巡るエコロジスト”松本英揮さん。自転車に乗って日本全国、そして世界100ヶ国以上の国を旅されたほど、超越した行動力のある方!すごい!!
ご自宅に招待され、美味しいハーブティーまでいただき、大変世話になりました。
ありがとうございました。
なおデジカメを忘れてしまい、写真を撮ることが出来ませんでした。申し訳ありません。
★以下インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC:まず、H-imagineさんの活動内容について教えてください。
松本:なんにもしてない、ひまじんだから(笑)。子供が、荒れたり事件をおこしたりうつ病になったり、今の社会はすごくおかしな方向に行っている。その理由は、子どものときから受験勉強や習い事で休日もなくとても忙しそうにしているから。子供から大人まで、定年になるまで目いっぱい忙しく働いて死んでいくと言うのがいまの世の中でしょ。このままじゃどうしようもない、それを変えるためにみんなが「ひまじん」になろうという想いと、日向の国のイメージ(イマジン)でH-imagineという名前にしました。
活動内容は主に環境学習。県内の子供達に、地球で何が起こっているかを伝え、どういう生き方をすればみんなが幸せになれるかを考えてもらいたいと思っています。それと、宮崎を地球の環境首都にしたい。1人1人の意識も大切ですが、街全体が素敵になることもすごく大事ですよね。そこで、宮崎市内に路面電車による街づくり計画「宮崎LRT(Light Rail Transit)計画」を提案しています。
今度やるのが植林です。何故植林かと言うと、木を植えた瞬間に「大地に根差す」という意味を感じることができるからです。5年10年経って成長した木を見ると、人間として自然に生かされていることの意味もわかり、生き方も、すごく楽しい形で本質に向かっていくことができます。川南に4000本の植樹を行う予定です。
でも「ひまじん」だからあまりカツカツとは活動していません。メンバーもそれぞれ仕事を持ち、いろんな役割をもって、ゆるやかに活動していますね。
CCC:松本さん以外のH-imagineメンバーについて教えてください。
松本:エコ建築家や、ビンのリサイクル講座を開いてリサイクルから技術に変える活動をしている方、宇宙人と話す女性(笑)、オーガニックパーマをしている美容師など、いろんな人がいます。女性であれば主婦や子育てなど、それぞれの立場からの視点の違いがあるため、それを大切にしながらNPO活動を行っています。
CCC:宮崎LRT計画についてですが、路面電車と引くことが、なぜ街づくりにつながるとお思いですか?
松本:ヨーロッパでは、交通の基本が路面電車・自転車です。環境モデルのひとつとして、スイスのバーゼルという街があります。街の中心には自家用車が走っておらず、水が流れています。橘通りとは違い、平日でもとても人が多いし、中心商店街は活気にあふれています。環境もいいし、人の流れもすごくいい。老若男女みんなが自然に交わることができる。宮崎をこんな街にしたいと思いました。このような街の影響で鹿児島や富山も、10年かけて路面電車の線路に芝生を敷いたんですよ。
CCC:確かに宮崎は交通が不便で、主な交通手段が自家用車になっていますね。
松本:宮崎市は、日本の県庁所在地では交通がワースト1になっています。自動車は環境にも良くないし、路面電車や自転車だけで生活できるのはとてもすばらしいことです。ドイツに20年前まで宮崎と同じように車だらけだった街もあったけど、今では道路を走るのはほとんど路面電車や自転車です。市長自らが自転車通勤を行い、市民にアピールして実現したことなのです。とあるシンポジウムでお会いした新宮崎市長の戸敷さんにも宮崎LRT計画に賛成していただき、この計画を進めて下さると約束してくれました。
CCC:宮崎でも不可能ではないということですね?
松本:もちろんです。地域改革については当然反対もあります。根本的な民主主義の意義とは、住民が何を望むかであり、現在の日本は民主主義とは言えません。昼間に行われる議会では、仕事を持つ一般住民が参加することはできず、密室的なものとなり、住民の本当の願いは実現できません。ヨーロッパのように、平日の夜間に議会を行うことで、仕事終わりの住民たちが参加し、彼らの願いが実現できるのです。
CCC:なるほど。先程自転車の話も出てきましたが、松本さんは自転車で100カ国以上の国を旅されたそうですね。自転車の旅についての想いはありますか?
松本:僕は子供のころから自転車が好きで、12歳のころから宮崎県内を旅していました。NPO活動を始めてから、国公立大学が独立法人化し(「これは文部科学省、つまり国が教育放棄をしたのと同様。先進国で国立大学がなくなるのはありえない」とのこと)、講師をしていた鹿児島大学から「交通費が出なくなった」と連絡を受け、自転車で通勤するようになりました。ちなみに僕の講義は1番人気で450人受講者がいます(笑)。自転車で行くうちにとても楽しくなり、長崎大学にも自転車で行くようになりました。長崎までは15時間半かかり、また坂道が多く、アップダウンがとてもきつい。
ロシア、アフリカ、サハラ、アマゾンも自転車で旅しました。宮崎から発信するだけでなく、そうやって世界中を旅しながら講演をしたり、その国の問題を解決するための提案を行ったりもします。いろんなところを実際に見ることによって、故郷である宮崎のこともより見えてきます。これは僕個人の考えではなく、団体全体としての考えです。
学生向けに格安のヨーロッパエコツアーも企画していて、毎年たくさんの学生や社会人が参加します。ヨーロッパの教育・環境・福祉の先進都市を具体的に、楽しんで見て欲しいです。世界一エコなホテル「ビクトリア」にも宿泊します。そして宮崎に帰ってきて、街づくりや故郷のために自分に何が出来るかを考える機会にして欲しいですね。社会起業支援サミットでのプレゼンテーションでもエコツアーのDVDを流して、会場の皆さんにも見てもらおうと思います。
また、自転車は健康にもいいですよ。ここ何年も病院行ってない。みんなが自転車を使うようになると病気にならないから医療費が減り、余った分を福祉に回すことだってできます。
CCC:まだ二十歳なのに車ばっかり使っている自分(井上)が恥ずかしいです…。ところで、H-imagineさんの活動理念というのはどういったものでしょうか?
松本:理念をもたないことが理念(笑)。「ひまになろう!」ってことかな、ひまじんだから。もっと自由にみんなが生きられたら、自然と変わっていくんじゃないかなと思っています。
一応窓口は環境NPOなんですが、いろんなことって全て繋がっているでしょ。今年やろうと思っているのが教育改革で、センター試験をなくすってことですね。
CCC:おおお!(感嘆)もっと前にやって欲しかったですね(笑)。
松本:2、3年遅かったかな?(笑)。僕の息子がいま中学2年生で、小学生のときから勉強が大変そうですが、それに意味があるかと言ったら、僕はNOだと思いますね。僕も高校時代に受験地獄の1番ひどい時期を体験しましたが、何かおかしいんじゃないかと思って。日本の社会が良くなっていくためにはセンター試験をなくす。なくせば、小中高校生の生活もガラッと変わります。その空いた時間に植林体験に参加したりとか、本当に大切なことができると思います。ヨーロッパの中学生なんて、自分でアルバイトして日本に来たりするもんね。かと言って学力が低いかといったらそうじゃない、逆に日本よりも高いですよね。子供時代に感性を育む生活をおくることが大事なんです。
年末にお茶の水女子大学で講演をしたとき、お茶の水女子大学附属小学校の副校長をされていた、古市憲一さんと初めてお会いしました。この方は受験というものをなくす運動を以前から行っており、「教育は教育現場で変えることはできないから政治を変えないといけない」という考えで意気投合しました。例えば、内申書やセンター試験、偏差値で合否を決めるのではなく、植林活動を行っただとか、講演会に行って実際に何か行動を起こしただとかを記した高校生の履歴書をつくることです。学力の比重を3分の1くらい落として、どういう考えをもって、どういうことを学びたいのかを重視するわけです。受験も1回だけでなく、3回くらいチャンスを与えたいとも考えています。古市さんはそのような具体的な提案もされていますが、僕も講演会などをやりながらそういう活動をしていこうと思っています。10年後、君達の子供さんの時代には受験がなくなっているかもね(笑)
息子にも、半分は無理矢理に旅をさせていました。嫌がることはありましたが、生きていくうえで、必ず将来的に役立つと考えてのことです。大自然に触れたり、様々な人と出会ったり、楽しい経験もいっぱいありました。そういう経験がないと、受験勉強や仕事ばかりで、目いっぱいの状態が定年まで続いてしまい、また柔軟な発想も出なくなってしまいます。
続きは、こちらから
インタビューにお答え下さったのは代表理事である“チャリで世界を巡るエコロジスト”松本英揮さん。自転車に乗って日本全国、そして世界100ヶ国以上の国を旅されたほど、超越した行動力のある方!すごい!!
ご自宅に招待され、美味しいハーブティーまでいただき、大変世話になりました。
ありがとうございました。
なおデジカメを忘れてしまい、写真を撮ることが出来ませんでした。申し訳ありません。
★以下インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC:まず、H-imagineさんの活動内容について教えてください。
松本:なんにもしてない、ひまじんだから(笑)。子供が、荒れたり事件をおこしたりうつ病になったり、今の社会はすごくおかしな方向に行っている。その理由は、子どものときから受験勉強や習い事で休日もなくとても忙しそうにしているから。子供から大人まで、定年になるまで目いっぱい忙しく働いて死んでいくと言うのがいまの世の中でしょ。このままじゃどうしようもない、それを変えるためにみんなが「ひまじん」になろうという想いと、日向の国のイメージ(イマジン)でH-imagineという名前にしました。
活動内容は主に環境学習。県内の子供達に、地球で何が起こっているかを伝え、どういう生き方をすればみんなが幸せになれるかを考えてもらいたいと思っています。それと、宮崎を地球の環境首都にしたい。1人1人の意識も大切ですが、街全体が素敵になることもすごく大事ですよね。そこで、宮崎市内に路面電車による街づくり計画「宮崎LRT(Light Rail Transit)計画」を提案しています。
今度やるのが植林です。何故植林かと言うと、木を植えた瞬間に「大地に根差す」という意味を感じることができるからです。5年10年経って成長した木を見ると、人間として自然に生かされていることの意味もわかり、生き方も、すごく楽しい形で本質に向かっていくことができます。川南に4000本の植樹を行う予定です。
でも「ひまじん」だからあまりカツカツとは活動していません。メンバーもそれぞれ仕事を持ち、いろんな役割をもって、ゆるやかに活動していますね。
CCC:松本さん以外のH-imagineメンバーについて教えてください。
松本:エコ建築家や、ビンのリサイクル講座を開いてリサイクルから技術に変える活動をしている方、宇宙人と話す女性(笑)、オーガニックパーマをしている美容師など、いろんな人がいます。女性であれば主婦や子育てなど、それぞれの立場からの視点の違いがあるため、それを大切にしながらNPO活動を行っています。
CCC:宮崎LRT計画についてですが、路面電車と引くことが、なぜ街づくりにつながるとお思いですか?
松本:ヨーロッパでは、交通の基本が路面電車・自転車です。環境モデルのひとつとして、スイスのバーゼルという街があります。街の中心には自家用車が走っておらず、水が流れています。橘通りとは違い、平日でもとても人が多いし、中心商店街は活気にあふれています。環境もいいし、人の流れもすごくいい。老若男女みんなが自然に交わることができる。宮崎をこんな街にしたいと思いました。このような街の影響で鹿児島や富山も、10年かけて路面電車の線路に芝生を敷いたんですよ。
CCC:確かに宮崎は交通が不便で、主な交通手段が自家用車になっていますね。
松本:宮崎市は、日本の県庁所在地では交通がワースト1になっています。自動車は環境にも良くないし、路面電車や自転車だけで生活できるのはとてもすばらしいことです。ドイツに20年前まで宮崎と同じように車だらけだった街もあったけど、今では道路を走るのはほとんど路面電車や自転車です。市長自らが自転車通勤を行い、市民にアピールして実現したことなのです。とあるシンポジウムでお会いした新宮崎市長の戸敷さんにも宮崎LRT計画に賛成していただき、この計画を進めて下さると約束してくれました。
CCC:宮崎でも不可能ではないということですね?
松本:もちろんです。地域改革については当然反対もあります。根本的な民主主義の意義とは、住民が何を望むかであり、現在の日本は民主主義とは言えません。昼間に行われる議会では、仕事を持つ一般住民が参加することはできず、密室的なものとなり、住民の本当の願いは実現できません。ヨーロッパのように、平日の夜間に議会を行うことで、仕事終わりの住民たちが参加し、彼らの願いが実現できるのです。
CCC:なるほど。先程自転車の話も出てきましたが、松本さんは自転車で100カ国以上の国を旅されたそうですね。自転車の旅についての想いはありますか?
松本:僕は子供のころから自転車が好きで、12歳のころから宮崎県内を旅していました。NPO活動を始めてから、国公立大学が独立法人化し(「これは文部科学省、つまり国が教育放棄をしたのと同様。先進国で国立大学がなくなるのはありえない」とのこと)、講師をしていた鹿児島大学から「交通費が出なくなった」と連絡を受け、自転車で通勤するようになりました。ちなみに僕の講義は1番人気で450人受講者がいます(笑)。自転車で行くうちにとても楽しくなり、長崎大学にも自転車で行くようになりました。長崎までは15時間半かかり、また坂道が多く、アップダウンがとてもきつい。
ロシア、アフリカ、サハラ、アマゾンも自転車で旅しました。宮崎から発信するだけでなく、そうやって世界中を旅しながら講演をしたり、その国の問題を解決するための提案を行ったりもします。いろんなところを実際に見ることによって、故郷である宮崎のこともより見えてきます。これは僕個人の考えではなく、団体全体としての考えです。
学生向けに格安のヨーロッパエコツアーも企画していて、毎年たくさんの学生や社会人が参加します。ヨーロッパの教育・環境・福祉の先進都市を具体的に、楽しんで見て欲しいです。世界一エコなホテル「ビクトリア」にも宿泊します。そして宮崎に帰ってきて、街づくりや故郷のために自分に何が出来るかを考える機会にして欲しいですね。社会起業支援サミットでのプレゼンテーションでもエコツアーのDVDを流して、会場の皆さんにも見てもらおうと思います。
また、自転車は健康にもいいですよ。ここ何年も病院行ってない。みんなが自転車を使うようになると病気にならないから医療費が減り、余った分を福祉に回すことだってできます。
CCC:まだ二十歳なのに車ばっかり使っている自分(井上)が恥ずかしいです…。ところで、H-imagineさんの活動理念というのはどういったものでしょうか?
松本:理念をもたないことが理念(笑)。「ひまになろう!」ってことかな、ひまじんだから。もっと自由にみんなが生きられたら、自然と変わっていくんじゃないかなと思っています。
一応窓口は環境NPOなんですが、いろんなことって全て繋がっているでしょ。今年やろうと思っているのが教育改革で、センター試験をなくすってことですね。
CCC:おおお!(感嘆)もっと前にやって欲しかったですね(笑)。
松本:2、3年遅かったかな?(笑)。僕の息子がいま中学2年生で、小学生のときから勉強が大変そうですが、それに意味があるかと言ったら、僕はNOだと思いますね。僕も高校時代に受験地獄の1番ひどい時期を体験しましたが、何かおかしいんじゃないかと思って。日本の社会が良くなっていくためにはセンター試験をなくす。なくせば、小中高校生の生活もガラッと変わります。その空いた時間に植林体験に参加したりとか、本当に大切なことができると思います。ヨーロッパの中学生なんて、自分でアルバイトして日本に来たりするもんね。かと言って学力が低いかといったらそうじゃない、逆に日本よりも高いですよね。子供時代に感性を育む生活をおくることが大事なんです。
年末にお茶の水女子大学で講演をしたとき、お茶の水女子大学附属小学校の副校長をされていた、古市憲一さんと初めてお会いしました。この方は受験というものをなくす運動を以前から行っており、「教育は教育現場で変えることはできないから政治を変えないといけない」という考えで意気投合しました。例えば、内申書やセンター試験、偏差値で合否を決めるのではなく、植林活動を行っただとか、講演会に行って実際に何か行動を起こしただとかを記した高校生の履歴書をつくることです。学力の比重を3分の1くらい落として、どういう考えをもって、どういうことを学びたいのかを重視するわけです。受験も1回だけでなく、3回くらいチャンスを与えたいとも考えています。古市さんはそのような具体的な提案もされていますが、僕も講演会などをやりながらそういう活動をしていこうと思っています。10年後、君達の子供さんの時代には受験がなくなっているかもね(笑)
息子にも、半分は無理矢理に旅をさせていました。嫌がることはありましたが、生きていくうえで、必ず将来的に役立つと考えてのことです。大自然に触れたり、様々な人と出会ったり、楽しい経験もいっぱいありました。そういう経験がないと、受験勉強や仕事ばかりで、目いっぱいの状態が定年まで続いてしまい、また柔軟な発想も出なくなってしまいます。
続きは、こちらから
2010年02月12日
【取材】NPO法人ドロップインセンターさま (前編)
本日は、NPO法人ドロップインセンター様へ取材に行かせていただきました。
インタビューに応じてくださったのは、現在(3代目)の理事長 藤崎路子さん、
2代目の理事長 黒田奈々さん、初代理事長 原田和代さんです。
みなさん、とても柔らかな雰囲気の中にも、凛とした筋があって、とても素敵でした。
また、子どもさんとも遊ばせていただき、スタッフの方には大変お世話になりました。
ありがとうございました。

(写真:とても楽しげな、こどもらんどのサイン)
♪゚インタビュー ここから+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪
CCC まずは、活動のきっかけについて教えてください。
原田 少し長くなりますがいいですか?(全員笑)。1998年にNPO法ができて、いろいろ勉強する機会がありました。当時、私たちはおやこ劇場という活動をしていたのですが、法律ができたとき、私たちのために法律ができた!と思いました。何かしようというときに、人間は変化がいやだというタイプと変化したいと思うタイプがいますよね。その中で変化したい、という人たち5人が集まって、2000年にNPO法人みやざき子ども文化センターを立ち上げました。4年間活動していく中で、本当にやりたかったことは何だっただろう、と考えることがしばしばありました。そのとき、自分自身の経験を思い出したんです。私は生まれが関西で、慣れない土地である宮崎で子育てする中で、孤立感や焦りを感じていました。子どもってこんなに泣くんだとか、そういったことで不安になり、話し相手は夫だけ。そんな状況で、ああ、大人の会話がしたいなと思いました。そんな経験を思い出すと、ああ、私がしたかったことは、親を支援することだと思いました。そこで、今の団体を2代目の理事長である黒田さんと刀根さんとで立ち上げました。
CCC なるほど。親の支援というのは、あまり聞かない支援だと思うのですが、どういうお考えで活動されていますか?
原田 子育てを考えることは、地域を耕すことだと思っています。子どものために地域づくりをしたいんです。子ども本当に幸せを感じられるためには、親が幸せでなくてはいけない、親が幸せになるためには、地域が幸せでなくてはいけない、ということです。
藤崎 そうです。子どものことを考えるということは、私たちの未来を考えることでもあるんです。
CCC そうですね。大人と子どもというのは連続していますよね。そういった親の支援に関する現在の活動について教えていただけますか?
藤崎 まず、子どもの預かりです。現在携わっている方が40人弱で、だいたいの方が有償ボランティアで、保育士などの資格を持った方もいます。
CCC 資格を持たないと、ボランティアできないのでしょうか?
藤崎 いえいえ、そんなことはありません。よくよく伺ってみると、看護士だった、とか保育士だった、とかいうこともありますが、それありきではありません。
原田 そうです。私たちはそういった支援者研修を年に50回ほど行っていますが、こういった研修を受けていただくことと、コミュニケーションがとれることが条件です。
私たちの活動ですが、年に144回の研修事業がメインです。平成21年度総会議会議案書を観ていただくとわかるのですが(はじめてこうした資料をいただきました)、親支援講座NPと書かれたものがメインです。NPというのは、Nobody’s Perfectというカナダで生まれたプログラムです。完璧な親なんていない、という考えをもとに、どんな親でも解決できる力がある、必要な情報を得る、お金がかからないことを三本柱に学びます。誰だって新米、必要なときに助けを借りていいんだよということなんです。私たちは、あくまでも助手席に座ります。運転するのは親自身です。親子の問題を解決できるのは親自身なのですから。

(写真:たくさんの絵本におもちゃ。ゆっくりくつろげる畳に寝っころがる親子連れの姿も)
CCC なるほど。とてもいいプログラムなんですね。そうした活動はどうやって運営されているのでしょうか?
藤崎 観ていただくとわかるとおり、市などの委託事業と福祉系の助成金でまかなっています。もちろん自主事業(利用者負担を含む)もあります。その組み合わせは、事業ごとに異なっています。
CCC なるほど。でもこれだけたくさんの委託や助成金をとられるというのはすごいですよね。
原田 やっぱり、福祉という分野は、行政が担う分野なのだろうと思います。ビジネス化しようとしても、やはり利用者の方に高額の負担は難しいですし、ビジネスの仕組みをもう少し考える必要はあるのですが、なかなか難しいと思っています。どなたが、ビジネス化できるように知恵をいただけませんか?
続きは後編へ。。。
インタビューに応じてくださったのは、現在(3代目)の理事長 藤崎路子さん、
2代目の理事長 黒田奈々さん、初代理事長 原田和代さんです。
みなさん、とても柔らかな雰囲気の中にも、凛とした筋があって、とても素敵でした。
また、子どもさんとも遊ばせていただき、スタッフの方には大変お世話になりました。
ありがとうございました。

(写真:とても楽しげな、こどもらんどのサイン)
♪゚インタビュー ここから+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪゚+。+゚♪
CCC まずは、活動のきっかけについて教えてください。
原田 少し長くなりますがいいですか?(全員笑)。1998年にNPO法ができて、いろいろ勉強する機会がありました。当時、私たちはおやこ劇場という活動をしていたのですが、法律ができたとき、私たちのために法律ができた!と思いました。何かしようというときに、人間は変化がいやだというタイプと変化したいと思うタイプがいますよね。その中で変化したい、という人たち5人が集まって、2000年にNPO法人みやざき子ども文化センターを立ち上げました。4年間活動していく中で、本当にやりたかったことは何だっただろう、と考えることがしばしばありました。そのとき、自分自身の経験を思い出したんです。私は生まれが関西で、慣れない土地である宮崎で子育てする中で、孤立感や焦りを感じていました。子どもってこんなに泣くんだとか、そういったことで不安になり、話し相手は夫だけ。そんな状況で、ああ、大人の会話がしたいなと思いました。そんな経験を思い出すと、ああ、私がしたかったことは、親を支援することだと思いました。そこで、今の団体を2代目の理事長である黒田さんと刀根さんとで立ち上げました。
CCC なるほど。親の支援というのは、あまり聞かない支援だと思うのですが、どういうお考えで活動されていますか?
原田 子育てを考えることは、地域を耕すことだと思っています。子どものために地域づくりをしたいんです。子ども本当に幸せを感じられるためには、親が幸せでなくてはいけない、親が幸せになるためには、地域が幸せでなくてはいけない、ということです。
藤崎 そうです。子どものことを考えるということは、私たちの未来を考えることでもあるんです。
CCC そうですね。大人と子どもというのは連続していますよね。そういった親の支援に関する現在の活動について教えていただけますか?
藤崎 まず、子どもの預かりです。現在携わっている方が40人弱で、だいたいの方が有償ボランティアで、保育士などの資格を持った方もいます。
CCC 資格を持たないと、ボランティアできないのでしょうか?
藤崎 いえいえ、そんなことはありません。よくよく伺ってみると、看護士だった、とか保育士だった、とかいうこともありますが、それありきではありません。
原田 そうです。私たちはそういった支援者研修を年に50回ほど行っていますが、こういった研修を受けていただくことと、コミュニケーションがとれることが条件です。
私たちの活動ですが、年に144回の研修事業がメインです。平成21年度総会議会議案書を観ていただくとわかるのですが(はじめてこうした資料をいただきました)、親支援講座NPと書かれたものがメインです。NPというのは、Nobody’s Perfectというカナダで生まれたプログラムです。完璧な親なんていない、という考えをもとに、どんな親でも解決できる力がある、必要な情報を得る、お金がかからないことを三本柱に学びます。誰だって新米、必要なときに助けを借りていいんだよということなんです。私たちは、あくまでも助手席に座ります。運転するのは親自身です。親子の問題を解決できるのは親自身なのですから。

(写真:たくさんの絵本におもちゃ。ゆっくりくつろげる畳に寝っころがる親子連れの姿も)
CCC なるほど。とてもいいプログラムなんですね。そうした活動はどうやって運営されているのでしょうか?
藤崎 観ていただくとわかるとおり、市などの委託事業と福祉系の助成金でまかなっています。もちろん自主事業(利用者負担を含む)もあります。その組み合わせは、事業ごとに異なっています。
CCC なるほど。でもこれだけたくさんの委託や助成金をとられるというのはすごいですよね。
原田 やっぱり、福祉という分野は、行政が担う分野なのだろうと思います。ビジネス化しようとしても、やはり利用者の方に高額の負担は難しいですし、ビジネスの仕組みをもう少し考える必要はあるのですが、なかなか難しいと思っています。どなたが、ビジネス化できるように知恵をいただけませんか?
続きは後編へ。。。
2010年02月12日
【取材】NPO法人宮崎文化本舗 石田達也さん (前編)
ダブルヘッダーで、NPO法人宮崎文化本舗さまに取材に行って参りました。
インタビューにお答えくださったのは、代表理事 石田達也さん。
映画が好きで、この業界に入られた石田さん。(お好きな映画は、いろいろあるけれど、強いて挙げるなら
「ガープの世界」と「あなただけ今晩は」とのこと)
NPOを立ち上げて10年が経過し、宮崎で(いや全国で)屈指のコミュニティビジネスを展開されている宮崎文化本舗さまにお話をうかがって参りました。
★以下 インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC 県内外で、非常に著名な文化本舗さんですが、現在の活動内容を教えてください。
石田 多岐にわたるのですが、大雑把に言えば、事務局の代行業務です。宮崎には市民活動をされている方がたくさんいますが、皆さんものすごく忙しいし、大変なんです。イベントをするにしても、講演会にするしても、諸連絡、マスコミ手配、チケットさばきなどをしなければならない。市民活動をされている人はだいたい、仕事を掛け持ちしている人が多いのですが、仕事中にそれらの電話がかかってきても、とれないのが現状です。ですから、こうした方々向けに事務局の代行を行っています。もう1つは、映画館の運営です。映画館は人口60万人いる鹿児島ですら成り立たない業界です。良質の映画を観ることは、文化的な機会を提供するということにも繋がります。また、人生を変えるきっかけを創ったり、そういう機会を創るという意味もあります。今はシネコン一辺倒時代ですが、みんながみんな、ハリウッド映画を観ればいいかというとそうではありませんから。売れなかったら、すぐやめるというのではありません。そもそもは、この映画館の運営の合間(?)をぬって事務局代行業を行っていましたが、今では事務局代行業の方が大きくなってきました。
CCC そもそもは、映画館(キネマ館)から始まったとお読みしました。映画館の運営と事務局代行とでは、その運営や組織、運営の仕組みが違うと思うのですが、どのような運営の仕方をされているのですか?
石田 映画というのは、先ほども申しましたように、芸術・文化のまちづくりには必要なんです。ですが、採算的に厳しいのが現実です。そこで始めたのが事務局代行ですが、これは、民間企業、商店街、行政などさまざまな方からご依頼があります。それぞれ求める内容が違いますので、それぞれ求められる内容に応じて組織形態も運営形態も変えています。ボランティア団体等の事務局を代行する場合には、こちらが持ち出しをすることもあるくらいです。今、宮崎では中間支援的な団体、NPOを支援する団体が求められていると思います。行政は資金的な面でバックアップしますが、広く浅く公平に行うことが求められています。ですが、実際に、NPOの中には人的支援を求めているところも多いのです。ですから、そういったニーズに応え、きちんと仕事、マネジメントをし、それに見合った経費をいただくというのが、私たちの運営の仕方です。
CCC なるほど。今までの事業の積み重ねで、事務局代行のノウハウを蓄積されて来られたのですね。収支計算書を拝読させていただいたのですが、すごい規模のお金が動いています。それでも敢えて、NPO法人でいらっしゃるのは、何か理由があるのですか?
石田 NPO法人というのは、手法であって目的ではありません。こだわっているわけではないですが、有限会社(筆者注:今は合同会社)や株式会社では、ボランティアができません。また、私たちは収益をあげ、当然課税の対象になっています。ボランティアと収益事業の双方を考えたときに、私たちに一番相応しいのはNPO法人だと判断しました。
CCC では、運営はボランティアの方が行っているのでしょうか?
石田 業務をまわしているのは、指定管理も含めて55人です。それから、事業ごとにボランティアを募って事業を行っています。ボランティアは登録制度ではなく、事業の関連性ごとに募った方が、それぞれの興味に基づいてできますので、そのような方法をとっています。
CCC 組織はどのような形態となっていますか?
石田 正会員(決定権がある会員)が18名、賛助会員が200〜300名です。賛助会員が多いのは、キネマ館の映画割引をつけているからですね(苦笑)。
NPO法人の場合、来るものを拒めない制度となっていますので、経営権を乗っ取られないように会費で線引きするようにしています。
CCC 近年、内閣府の緊急雇用対策などでも、社会起業(社会的企業)で地域の雇用を創出できないかと考えられています。また、僕たち大学生の就職も大変になってきています。文化本舗さんは、55人もの方が働いていらっしゃり、地域の中でも非常に大きな組織だと思うのですが、地域の働き口となっていることについて、文化本舗さんが考えていらっしゃることがあれば、教えてください。
石田 私たちの中で基本となる考え方は、「人が動けば金が動く」ということです。人が動くような事業を提案してくれる人であれば、学生であれ、社会人であれ、大歓迎なわけです。もちろん、対象とする「人」が誰か、ということもあります。ですが、いずれにしても、就職しても、合うか合わないか、の世界です。今の若い人は合わなければ、半年で辞めてしまう。だから、若い人には、どんどん提案して、自分でどんどん事業を創れと言っています。事業を創るということは、計画を考え、予算を採ってきて、というところが基本ですが、それができるやりがいがあるはずです。例えば、先週まで開催されていたムーミン展ですが、宮崎で3週間開催して、入場料収入と入場料の1.5倍の物販売上げを上げました。ニーズがあるところには、事業が生まれるチャンスがあるわけです。私たち宮崎文化本舗では、23歳から60歳までの人が働いています。30代から40代までが一番多いですが、今高岡で、地元の人たちと一緒になってがんばっているのは、20代の人です。最初、インターンで私たちのところに入ってきたのですが、インターンのときに、助成金の200万円を自由に使って事業をしてもいいよ、と言いました。そのかわり、責任もきちんととってくれと。そうしたところ、きちんと形にでき、事業として着地をして、今、宮崎文化本舗で働いています。
後編へ続く・・・
インタビューにお答えくださったのは、代表理事 石田達也さん。
映画が好きで、この業界に入られた石田さん。(お好きな映画は、いろいろあるけれど、強いて挙げるなら
「ガープの世界」と「あなただけ今晩は」とのこと)
NPOを立ち上げて10年が経過し、宮崎で(いや全国で)屈指のコミュニティビジネスを展開されている宮崎文化本舗さまにお話をうかがって参りました。
★以下 インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC 県内外で、非常に著名な文化本舗さんですが、現在の活動内容を教えてください。
石田 多岐にわたるのですが、大雑把に言えば、事務局の代行業務です。宮崎には市民活動をされている方がたくさんいますが、皆さんものすごく忙しいし、大変なんです。イベントをするにしても、講演会にするしても、諸連絡、マスコミ手配、チケットさばきなどをしなければならない。市民活動をされている人はだいたい、仕事を掛け持ちしている人が多いのですが、仕事中にそれらの電話がかかってきても、とれないのが現状です。ですから、こうした方々向けに事務局の代行を行っています。もう1つは、映画館の運営です。映画館は人口60万人いる鹿児島ですら成り立たない業界です。良質の映画を観ることは、文化的な機会を提供するということにも繋がります。また、人生を変えるきっかけを創ったり、そういう機会を創るという意味もあります。今はシネコン一辺倒時代ですが、みんながみんな、ハリウッド映画を観ればいいかというとそうではありませんから。売れなかったら、すぐやめるというのではありません。そもそもは、この映画館の運営の合間(?)をぬって事務局代行業を行っていましたが、今では事務局代行業の方が大きくなってきました。
CCC そもそもは、映画館(キネマ館)から始まったとお読みしました。映画館の運営と事務局代行とでは、その運営や組織、運営の仕組みが違うと思うのですが、どのような運営の仕方をされているのですか?
石田 映画というのは、先ほども申しましたように、芸術・文化のまちづくりには必要なんです。ですが、採算的に厳しいのが現実です。そこで始めたのが事務局代行ですが、これは、民間企業、商店街、行政などさまざまな方からご依頼があります。それぞれ求める内容が違いますので、それぞれ求められる内容に応じて組織形態も運営形態も変えています。ボランティア団体等の事務局を代行する場合には、こちらが持ち出しをすることもあるくらいです。今、宮崎では中間支援的な団体、NPOを支援する団体が求められていると思います。行政は資金的な面でバックアップしますが、広く浅く公平に行うことが求められています。ですが、実際に、NPOの中には人的支援を求めているところも多いのです。ですから、そういったニーズに応え、きちんと仕事、マネジメントをし、それに見合った経費をいただくというのが、私たちの運営の仕方です。
CCC なるほど。今までの事業の積み重ねで、事務局代行のノウハウを蓄積されて来られたのですね。収支計算書を拝読させていただいたのですが、すごい規模のお金が動いています。それでも敢えて、NPO法人でいらっしゃるのは、何か理由があるのですか?
石田 NPO法人というのは、手法であって目的ではありません。こだわっているわけではないですが、有限会社(筆者注:今は合同会社)や株式会社では、ボランティアができません。また、私たちは収益をあげ、当然課税の対象になっています。ボランティアと収益事業の双方を考えたときに、私たちに一番相応しいのはNPO法人だと判断しました。
CCC では、運営はボランティアの方が行っているのでしょうか?
石田 業務をまわしているのは、指定管理も含めて55人です。それから、事業ごとにボランティアを募って事業を行っています。ボランティアは登録制度ではなく、事業の関連性ごとに募った方が、それぞれの興味に基づいてできますので、そのような方法をとっています。
CCC 組織はどのような形態となっていますか?
石田 正会員(決定権がある会員)が18名、賛助会員が200〜300名です。賛助会員が多いのは、キネマ館の映画割引をつけているからですね(苦笑)。
NPO法人の場合、来るものを拒めない制度となっていますので、経営権を乗っ取られないように会費で線引きするようにしています。
CCC 近年、内閣府の緊急雇用対策などでも、社会起業(社会的企業)で地域の雇用を創出できないかと考えられています。また、僕たち大学生の就職も大変になってきています。文化本舗さんは、55人もの方が働いていらっしゃり、地域の中でも非常に大きな組織だと思うのですが、地域の働き口となっていることについて、文化本舗さんが考えていらっしゃることがあれば、教えてください。
石田 私たちの中で基本となる考え方は、「人が動けば金が動く」ということです。人が動くような事業を提案してくれる人であれば、学生であれ、社会人であれ、大歓迎なわけです。もちろん、対象とする「人」が誰か、ということもあります。ですが、いずれにしても、就職しても、合うか合わないか、の世界です。今の若い人は合わなければ、半年で辞めてしまう。だから、若い人には、どんどん提案して、自分でどんどん事業を創れと言っています。事業を創るということは、計画を考え、予算を採ってきて、というところが基本ですが、それができるやりがいがあるはずです。例えば、先週まで開催されていたムーミン展ですが、宮崎で3週間開催して、入場料収入と入場料の1.5倍の物販売上げを上げました。ニーズがあるところには、事業が生まれるチャンスがあるわけです。私たち宮崎文化本舗では、23歳から60歳までの人が働いています。30代から40代までが一番多いですが、今高岡で、地元の人たちと一緒になってがんばっているのは、20代の人です。最初、インターンで私たちのところに入ってきたのですが、インターンのときに、助成金の200万円を自由に使って事業をしてもいいよ、と言いました。そのかわり、責任もきちんととってくれと。そうしたところ、きちんと形にでき、事業として着地をして、今、宮崎文化本舗で働いています。
後編へ続く・・・
2010年02月12日
【取材】合同会社らくがきART 佐藤健郎さん 前編
本日は、合同会社らくがきARTさんに取材に行って参りました。
インタビューにお答えいただいたのは、代表クリエーターの佐藤健郎さん。
石ノ森章太郎に感銘を受け、クリエーターの道に入ったという佐藤さん。
インタビュー当日は、同じく漫画好きのスタッフ井上と話が盛り上がっておりました。
★以下インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC 本社は東京のようですが、宮崎でも活動をされているんですね。
佐藤 はい。当初、僕一人でNPOとして、2年ほど大分で活動していたのですが、東京・滋賀のメンバーとともに2009年7月に設立しました。活動範囲としては、東京、滋賀、大分、そして、昨年秋に僕が宮崎に引っ越してきたこともあって、宮崎ということになります。ただ、今年メンバーの都合もあって、東京は少しお休みします。ですから、宮崎での活動に力を入れ、地方が都市圏へ向けて発信していく活動をしていきたいと思っています。
CCC 従業員は何名ですか?
佐藤 当初は7名だったのですが、現在は4名です。
CCC 活動のきっかけを教えてください。
佐藤 もともと僕は、会社勤めをしながらアート作品を創っていました。ある日、ある子どもさんのらくがきを目にして、これをアート作品にしてみたいと思ったんです。その作品が、この「のけぞりピエロ」なんです(と作品を指差してくださる)。こういう作品をいくつか創っていたら、それを売ってほしいという人が何人か出てきました。作品を販売したときに、その売上げを僕一人で独占するのではなくて、子どもが書いたらくがきを元にして創ったのだから、子どもに対して何かを返さないといけないと思いました。そこで、売上げの半分を自分に、半分を子どもに、という考えが生まれ、実際にそうしました。
この仕組みを事業化できないかなと考えたとき、高校生の時のことを思い出しました。僕は芸術系の大学に進みたかったけれど、僕の家にはそんな経済力はありませんでした。もし、このらくがきを描くことによって積みたてられた奨学金とかがあったら、その芸術系の大学へ行きたいという夢や、ニューヨークへ行ってみたいという夢に挑戦しようとする資金になりはしないかと思いました。これが、今の「らくがきアート夢・自立支援奨学金」のおおもとです。
CCC 奨学金には返済の義務があるんですか?
佐藤 いえいえ、ありません。お子さんが描いたらくがきの報酬ですから。
CCC なるほど。子どもと大人の共同作業みたいな感じですね。サイトを拝見すると「子どもの夢とセッションしよう」というフレーズがあるのですが、これもそういった意味なのですか?
佐藤 そうです。セッションするということは、上下関係がない、ということです。上下関係なく、子どもが描いた絵を、芸術家が見た瞬間に何かを感じ、それを表現していく。出会った瞬間の、一番最初の感情を大切にして、何かを生み出していくということです。例えば、先ほどの「のけぞりピエロ」も、らくがき原画を見た人は、イルカとか、魚とか、いろんなことを言います。でも、僕は見た瞬間に「ピエロ」に見えたんです。だから、こういうセッションになりました。

(写真:のけぞりピエロとその原画)
CCC 「子どもの夢とセッション」することの前提として、社員皆さんの子どもの頃の夢を会社案内に書かれていますね。これにはどういった意図があるんですか?
佐藤 子どもの夢を大人が一緒にかなえる手伝いをする、という当社の基本的な考え方が反映されています。今の自分は、子どもの頃からの延長線にあります。僕の夢は、「石ノ森章太郎のような詩的な漫画家」でした。小学校5年生の頃になんとなく買った「サイボーグ009」が人生の出発点だからです。読んだ瞬間に人生観が変わりました。
CCC サイボーグ009ですか。それで、「世界平和」ということがサイトに書いてあったのでしょうか?
佐藤 世界平和というと、とても大きなことだと思われがちですが、例えば、戦争の指導者は、おそらく兵士たちに、自分たちが勝利するために邪魔をする人を排除せよ、と命じると思うんです。隣の国の子どもを殺せ、とは命じないと思うんです。つまり、大人が子どもを意識する環境ができたら、隣の国の子どもだろうが、子どもという存在を兵士が目にした時に、葛藤することができるのではないだろうかと思うのです。
僕たちは、政治のシステムをなかなか代えることができません。ただ、僕たちの活動によって、兵士が子どもに引き金を弾く前に、ためらう瞬間を創ることができると思っています。だから、もし政治の道具に使ってもらえるのであれば、それでもいいと思っているんです。エジソンは豆電球を創りました。でも豆電球の存在だけでは、今のような社会にはなっていないと思うんです。車のメーカー、照明器具のメーカー、そういった人たちが豆電球を使って何かをしようと思ったおかげで、今の社会があるのではないかと思います。だから、らくがきARTは、まだ豆電球なんです。それを使って何かしようとしてくれる人がいて、初めて活かされると思っています。世界中の日常生活で使われているものに、らくがきARTを使って、常に子どもを感じられるものを創ったら、社会も変わっていくのではないかと思います。
インタビューの内容は、後編に続く
インタビューにお答えいただいたのは、代表クリエーターの佐藤健郎さん。
石ノ森章太郎に感銘を受け、クリエーターの道に入ったという佐藤さん。
インタビュー当日は、同じく漫画好きのスタッフ井上と話が盛り上がっておりました。
★以下インタビュー★+。。。+★+。。。+★+。。。+★+。。。+★
CCC 本社は東京のようですが、宮崎でも活動をされているんですね。
佐藤 はい。当初、僕一人でNPOとして、2年ほど大分で活動していたのですが、東京・滋賀のメンバーとともに2009年7月に設立しました。活動範囲としては、東京、滋賀、大分、そして、昨年秋に僕が宮崎に引っ越してきたこともあって、宮崎ということになります。ただ、今年メンバーの都合もあって、東京は少しお休みします。ですから、宮崎での活動に力を入れ、地方が都市圏へ向けて発信していく活動をしていきたいと思っています。
CCC 従業員は何名ですか?
佐藤 当初は7名だったのですが、現在は4名です。
CCC 活動のきっかけを教えてください。
佐藤 もともと僕は、会社勤めをしながらアート作品を創っていました。ある日、ある子どもさんのらくがきを目にして、これをアート作品にしてみたいと思ったんです。その作品が、この「のけぞりピエロ」なんです(と作品を指差してくださる)。こういう作品をいくつか創っていたら、それを売ってほしいという人が何人か出てきました。作品を販売したときに、その売上げを僕一人で独占するのではなくて、子どもが書いたらくがきを元にして創ったのだから、子どもに対して何かを返さないといけないと思いました。そこで、売上げの半分を自分に、半分を子どもに、という考えが生まれ、実際にそうしました。
この仕組みを事業化できないかなと考えたとき、高校生の時のことを思い出しました。僕は芸術系の大学に進みたかったけれど、僕の家にはそんな経済力はありませんでした。もし、このらくがきを描くことによって積みたてられた奨学金とかがあったら、その芸術系の大学へ行きたいという夢や、ニューヨークへ行ってみたいという夢に挑戦しようとする資金になりはしないかと思いました。これが、今の「らくがきアート夢・自立支援奨学金」のおおもとです。
CCC 奨学金には返済の義務があるんですか?
佐藤 いえいえ、ありません。お子さんが描いたらくがきの報酬ですから。
CCC なるほど。子どもと大人の共同作業みたいな感じですね。サイトを拝見すると「子どもの夢とセッションしよう」というフレーズがあるのですが、これもそういった意味なのですか?
佐藤 そうです。セッションするということは、上下関係がない、ということです。上下関係なく、子どもが描いた絵を、芸術家が見た瞬間に何かを感じ、それを表現していく。出会った瞬間の、一番最初の感情を大切にして、何かを生み出していくということです。例えば、先ほどの「のけぞりピエロ」も、らくがき原画を見た人は、イルカとか、魚とか、いろんなことを言います。でも、僕は見た瞬間に「ピエロ」に見えたんです。だから、こういうセッションになりました。

(写真:のけぞりピエロとその原画)
CCC 「子どもの夢とセッション」することの前提として、社員皆さんの子どもの頃の夢を会社案内に書かれていますね。これにはどういった意図があるんですか?
佐藤 子どもの夢を大人が一緒にかなえる手伝いをする、という当社の基本的な考え方が反映されています。今の自分は、子どもの頃からの延長線にあります。僕の夢は、「石ノ森章太郎のような詩的な漫画家」でした。小学校5年生の頃になんとなく買った「サイボーグ009」が人生の出発点だからです。読んだ瞬間に人生観が変わりました。
CCC サイボーグ009ですか。それで、「世界平和」ということがサイトに書いてあったのでしょうか?
佐藤 世界平和というと、とても大きなことだと思われがちですが、例えば、戦争の指導者は、おそらく兵士たちに、自分たちが勝利するために邪魔をする人を排除せよ、と命じると思うんです。隣の国の子どもを殺せ、とは命じないと思うんです。つまり、大人が子どもを意識する環境ができたら、隣の国の子どもだろうが、子どもという存在を兵士が目にした時に、葛藤することができるのではないだろうかと思うのです。
僕たちは、政治のシステムをなかなか代えることができません。ただ、僕たちの活動によって、兵士が子どもに引き金を弾く前に、ためらう瞬間を創ることができると思っています。だから、もし政治の道具に使ってもらえるのであれば、それでもいいと思っているんです。エジソンは豆電球を創りました。でも豆電球の存在だけでは、今のような社会にはなっていないと思うんです。車のメーカー、照明器具のメーカー、そういった人たちが豆電球を使って何かをしようと思ったおかげで、今の社会があるのではないかと思います。だから、らくがきARTは、まだ豆電球なんです。それを使って何かしようとしてくれる人がいて、初めて活かされると思っています。世界中の日常生活で使われているものに、らくがきARTを使って、常に子どもを感じられるものを創ったら、社会も変わっていくのではないかと思います。
インタビューの内容は、後編に続く
2010年02月08日
【取材】有限会社綾わくわくファーム 濱田倫紀さん(後編)
前編はこちらから。
CCC さて、そろそろ時間も迫ってきたので、いくつかお尋ねをしたいのですが、まず収益事業について伺いたいと思います。先ほどのイベントの他に何かなさっていますか?
濱田 まず、コンシェルジュをしています。おとなの長旅というパッケージツアーですが、実は私たちが人気ナンバーワンなんです。
CCC 湯布院や阿蘇などを押さえてですか?
濱田 そうなんです。できるだけ4人単位で申込んでいただき、アグリライフを楽しんでいただきます。今都会の人が求めているのは、「農業」ではなくて「農的暮らし」なんですね。それも、おしゃれな農的暮らしなんです。グリーンツーリズムのうちうまくいっていないところは、やはりその点を考慮しないように思えます。例えば、野菜の植え方一つにしても、うちの近くの方は、とにかく一寸違わず真っ直ぐに野菜を植えます。それはもう芸術的です。そのくらいの神経でやらないとウケないということです。
それから、もう一つクラインガルテンというのをしています。
CCC クラインガルテン。小さな庭、ということですか?
濱田 そうです。1年契約の貸し農園です。15坪で月1万です。これは宮崎としてはとても高いのですが、スタッフが手を入れ、管理をし、また写真で状況をお伝えしたり、実際に農園に来られたときに農業指導をしたりします。そのコストを考えて設定した値段です。でも、これもまだしっかり宣伝していないにもかかわらず、もう既に申込があります。
また、私たちは、MRTラジオの放送スタジオを持っているのですが、完全にわくわくファーム(民間)で設立し、その後の放送料を綾町と民間スポンサーで維持しています。これで公も民間の宣伝を自由にできる訳です。(設立時には100万近くかかり、放送料は月25万円です。)

(写真:綾わくわくファームには、綾在住の職人さんが造られた雑貨や農に関する書籍が措かれている)
CCC なるほど。みんなでシェアすること、そして、無理しないこと。これがキーワードですね。
濱田 そうです。そして、待つこと、です。
CCC (またまた一同感心)。時間も迫ってきましたので、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、今の活動で障害になっていることを教えていただきたいということです。もう1つは、あったらいいなという制度がありましたら、教えてください。
濱田 障害になっていることはありません。
CCC (スタッフからおお〜という声があがる)
濱田 それから、あったらいいなという制度は、固定資産税などの減免制度です。例えば、商店街には、今空き地や空き店舗が多くなっています。その空き地に、野菜などを植えてみたらいいんじゃないかと思うんです。そして、鹿児島のやねだんのようにビジネス化してみる。その際に、土地に対する課税等を免除あるいは減じてほしいということです。
それから、皆さんに伝えたいことがあるんですが、皆さんも何かやってみたらいかがですか?ということです。ぜひソーシャルビジネスに興味を持ったのだから、何かされてみたらいいですよ。
CCC はい、がんばります。

(濱田さんを囲んで)
***以上取材***
当日は、大勢で押し掛けてしまいましたが、濱田さんの生き方そのものに、スタッフ一同感動しながらお話を伺いました。
また、お土産にご自身で書かれた書籍までいただきまして、ありがとうございました。
スタッフ一同、また勉強させていただきたいと思います。
インタビュー:井上、吉池
○基本情報
■団体名 有限会社綾わくわくファーム
■代表取締役 濱田倫紀
■所在地 東諸県郡綾町大字北俣2455-3
■ホームページ http://www.ayadore.jp/
○合わせて読みたい
■スタッフブログ http://ayadore.blog114.fc2.com/
■宮崎Webチャンネルのインタビュー http://www.miyazaki.ch/contents/?catid=137&itemid=1371
■おとなの長旅 http://www.nagatabi.jp/2009/program/aya.html
■隣人まつり http://www.rinjinmatsuri.jp/main/
■やねだん http://www.yanedan.com/index.html
CCC さて、そろそろ時間も迫ってきたので、いくつかお尋ねをしたいのですが、まず収益事業について伺いたいと思います。先ほどのイベントの他に何かなさっていますか?
濱田 まず、コンシェルジュをしています。おとなの長旅というパッケージツアーですが、実は私たちが人気ナンバーワンなんです。
CCC 湯布院や阿蘇などを押さえてですか?
濱田 そうなんです。できるだけ4人単位で申込んでいただき、アグリライフを楽しんでいただきます。今都会の人が求めているのは、「農業」ではなくて「農的暮らし」なんですね。それも、おしゃれな農的暮らしなんです。グリーンツーリズムのうちうまくいっていないところは、やはりその点を考慮しないように思えます。例えば、野菜の植え方一つにしても、うちの近くの方は、とにかく一寸違わず真っ直ぐに野菜を植えます。それはもう芸術的です。そのくらいの神経でやらないとウケないということです。
それから、もう一つクラインガルテンというのをしています。
CCC クラインガルテン。小さな庭、ということですか?
濱田 そうです。1年契約の貸し農園です。15坪で月1万です。これは宮崎としてはとても高いのですが、スタッフが手を入れ、管理をし、また写真で状況をお伝えしたり、実際に農園に来られたときに農業指導をしたりします。そのコストを考えて設定した値段です。でも、これもまだしっかり宣伝していないにもかかわらず、もう既に申込があります。
また、私たちは、MRTラジオの放送スタジオを持っているのですが、完全にわくわくファーム(民間)で設立し、その後の放送料を綾町と民間スポンサーで維持しています。これで公も民間の宣伝を自由にできる訳です。(設立時には100万近くかかり、放送料は月25万円です。)

(写真:綾わくわくファームには、綾在住の職人さんが造られた雑貨や農に関する書籍が措かれている)
CCC なるほど。みんなでシェアすること、そして、無理しないこと。これがキーワードですね。
濱田 そうです。そして、待つこと、です。
CCC (またまた一同感心)。時間も迫ってきましたので、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、今の活動で障害になっていることを教えていただきたいということです。もう1つは、あったらいいなという制度がありましたら、教えてください。
濱田 障害になっていることはありません。
CCC (スタッフからおお〜という声があがる)
濱田 それから、あったらいいなという制度は、固定資産税などの減免制度です。例えば、商店街には、今空き地や空き店舗が多くなっています。その空き地に、野菜などを植えてみたらいいんじゃないかと思うんです。そして、鹿児島のやねだんのようにビジネス化してみる。その際に、土地に対する課税等を免除あるいは減じてほしいということです。
それから、皆さんに伝えたいことがあるんですが、皆さんも何かやってみたらいかがですか?ということです。ぜひソーシャルビジネスに興味を持ったのだから、何かされてみたらいいですよ。
CCC はい、がんばります。

(濱田さんを囲んで)
***以上取材***
当日は、大勢で押し掛けてしまいましたが、濱田さんの生き方そのものに、スタッフ一同感動しながらお話を伺いました。
また、お土産にご自身で書かれた書籍までいただきまして、ありがとうございました。
スタッフ一同、また勉強させていただきたいと思います。
インタビュー:井上、吉池
○基本情報
■団体名 有限会社綾わくわくファーム
■代表取締役 濱田倫紀
■所在地 東諸県郡綾町大字北俣2455-3
■ホームページ http://www.ayadore.jp/
○合わせて読みたい
■スタッフブログ http://ayadore.blog114.fc2.com/
■宮崎Webチャンネルのインタビュー http://www.miyazaki.ch/contents/?catid=137&itemid=1371
■おとなの長旅 http://www.nagatabi.jp/2009/program/aya.html
■隣人まつり http://www.rinjinmatsuri.jp/main/
■やねだん http://www.yanedan.com/index.html
2010年02月08日
【取材】有限会社綾わくわくファーム 濱田倫紀さん(前編)
本日は、有限会社綾わくわくファーム様に取材に行って参りました。
インタビューにお答えいただいたのは、代表取締役の濱田倫紀さん。
さっそうと登場された濱田さん。
とてもおしゃれで、ダンディーで、私たちは圧倒されつつも、
早速インタビューを始めさせていただきました。
**以下取材内容***
CCC まずは会社のことからお伺いしたいのですが、従業員は何人でいらっしゃいますか?
濱田 従業員は一人もいません。
CCC (一同、びっくり)。
濱田 というよりも、正社員にはなっていないということです。娘が手伝ってくれていたのですが、このたび独立しました。ですが、いろんな人が手伝ってくれています。今、メインで手伝ってくれているのは、3人です。非常勤職員ですね。この人たちは、とても面白い働き方をしています。例えば、今日はキッチンの予約がないので休みます、とか、今日は儲かったから、営業時間を切り上げて15時で帰ろう、とか。ふいといなくなったと思ったら、東京で演劇三昧だったりとか。まあ、楽しく働いているのではないでしょうか。
CCC (これまた、一同びっくり)。
濱田 私たちの働き方(商売)は、「待つ」ということがキーワードです。待つことができれば、ゆとりができる。そのゆとりというのは、自分の身の丈にあった、ということでもあります。たとえば、若い頃ですと、すごく儲けたいと思う。儲けたいと思えば、スピードが必要になる。スピードを求めると次から次へとお金がいる、ということなんです。つまり、自分にとって無理の無い、ちょうどいい働き方があるということです。そして、そういうせくせくしないという発想は「スローライフ」に繋がるわけです。

(暖炉に火をともしていただき、あたたかな時間を過ごす)
CCC なるほど(一同感心)。そもそも、スローフードとはイタリアから始まった考え方だと書いてありましたが、濱田さんが考えるスローフードというのはどういったものでしょうか?
濱田 私が考えるスローフードとは、その土地に活気を与え、郷土の社会性を高める食品だ、と思います。宮崎にはおいしいものがたくさんあり、それを地元の人が食べる。おいしいものを大阪や東京に送らない、ということです。
CCC 最近、よく言われる地産地消ということでしょうか?
濱田 地産地消は、組織的、集団的な運動で、行政やJA主導です。スローフード運動は、生産者と消費者の間の運動です。
CCC 身土不二。初めて聴く言葉です。
濱田 身土不二の身は身体、土は風土、それが不二(不可分)であるということ、つまり、その土地と人間とは一体である、という考え方です。その土地とは、四里四方、人が歩ける距離のことです。
CCC それでは次に、展開されている事業についてお伺いしたいと思います。サイトで拝見すると、教育部門、イベント部門、地域産業振興部門、環境保護推進部門の4つの事業を展開されているようですが、最も力を入れていらっしゃる事業は何でしょうか?
濱田 食育とイベント部門です。食育については、綾スローフード協会の会長をしているのですが、本場イタリアのように、「食の大学」でありたいと思っています。食にまつわるあらゆる情報を集め、発信していきたいと思っています。イベント部門では、まず「スローフードまつり」というのを開催しています。綾町では6カ所参加してくれているのですが、イタリアにならって、綾在住の陶芸家が造った焼酎用のグラス(ワイングラスのこともある)を、同じく綾在住の織物家が創ったバッグに入れ、それを首から(ポシェットのように)ぶら下げて、10時〜16時まで、食べて、飲んで、をやります。チケット代は6,000円ですが、かなり人気があります。初めた頃は参加団体がそれほど多くなかったのですが、今では道沿いに出店が出たり、綾のお箸やさんが創ったマイ箸が売れたりと、まちの産業が次から次へと発展していっています。綾町には長らく、観光協会というのはなかったのですが、そもそもこうした観光を扱う課は、産業観光課です。つまり、産業と観光を結びつけることが大切だという考えでしょう。その他のイベントとしては、「隣人まつり」というのをやっています。これは、ソトコトという雑誌がノウハウを持っているのですが、要は近くの人を集めて、パーティーしましょう、というものです。現在では綾町の人に限定して開催しているのですが、出席した方からは、「あら、あなたも綾なの?」という声が聴かれるくらいに、皆さん隣近所のことをご存知ないんです。というのも、綾町は県外から移住してきた方も多いからでしょうね。

(写真:とてもおしゃれなキッチン)
CCC 地域における活動をとても大切にされているんですね。
濱田 そうですね。こうした考えは、もともと綾町長であった合田町長の考えによるのではないかと思います。合田町長は、非常に(政治)哲学がしっかりされていて、住民というのは怠惰だから、ニーズに答えてはいけない。行政の長というのは、住民を導かなくてはならないのだ、というお考えで動いていらした。だからこそ、1988年に有機農業条例を制定されたり、自治公民館の合田方式(1つの区を250〜300戸にする方式で、その中から公民館長を選出、毎月1回公民館長会議を開く)を開発されたりしたのだろうと思います。またアメリカにならって、コミュニティスクールを開き、中学生に地域のことを考えるきっかけを与えるということもされていました。郷土愛を育てることが、人としての基本だと考えられていたのでしょう。
後編へ続く。。。
インタビューにお答えいただいたのは、代表取締役の濱田倫紀さん。
さっそうと登場された濱田さん。
とてもおしゃれで、ダンディーで、私たちは圧倒されつつも、
早速インタビューを始めさせていただきました。
**以下取材内容***
CCC まずは会社のことからお伺いしたいのですが、従業員は何人でいらっしゃいますか?
濱田 従業員は一人もいません。
CCC (一同、びっくり)。
濱田 というよりも、正社員にはなっていないということです。娘が手伝ってくれていたのですが、このたび独立しました。ですが、いろんな人が手伝ってくれています。今、メインで手伝ってくれているのは、3人です。非常勤職員ですね。この人たちは、とても面白い働き方をしています。例えば、今日はキッチンの予約がないので休みます、とか、今日は儲かったから、営業時間を切り上げて15時で帰ろう、とか。ふいといなくなったと思ったら、東京で演劇三昧だったりとか。まあ、楽しく働いているのではないでしょうか。
CCC (これまた、一同びっくり)。
濱田 私たちの働き方(商売)は、「待つ」ということがキーワードです。待つことができれば、ゆとりができる。そのゆとりというのは、自分の身の丈にあった、ということでもあります。たとえば、若い頃ですと、すごく儲けたいと思う。儲けたいと思えば、スピードが必要になる。スピードを求めると次から次へとお金がいる、ということなんです。つまり、自分にとって無理の無い、ちょうどいい働き方があるということです。そして、そういうせくせくしないという発想は「スローライフ」に繋がるわけです。

(暖炉に火をともしていただき、あたたかな時間を過ごす)
CCC なるほど(一同感心)。そもそも、スローフードとはイタリアから始まった考え方だと書いてありましたが、濱田さんが考えるスローフードというのはどういったものでしょうか?
濱田 私が考えるスローフードとは、その土地に活気を与え、郷土の社会性を高める食品だ、と思います。宮崎にはおいしいものがたくさんあり、それを地元の人が食べる。おいしいものを大阪や東京に送らない、ということです。
CCC 最近、よく言われる地産地消ということでしょうか?
濱田 地産地消は、組織的、集団的な運動で、行政やJA主導です。スローフード運動は、生産者と消費者の間の運動です。
CCC 身土不二。初めて聴く言葉です。
濱田 身土不二の身は身体、土は風土、それが不二(不可分)であるということ、つまり、その土地と人間とは一体である、という考え方です。その土地とは、四里四方、人が歩ける距離のことです。
CCC それでは次に、展開されている事業についてお伺いしたいと思います。サイトで拝見すると、教育部門、イベント部門、地域産業振興部門、環境保護推進部門の4つの事業を展開されているようですが、最も力を入れていらっしゃる事業は何でしょうか?
濱田 食育とイベント部門です。食育については、綾スローフード協会の会長をしているのですが、本場イタリアのように、「食の大学」でありたいと思っています。食にまつわるあらゆる情報を集め、発信していきたいと思っています。イベント部門では、まず「スローフードまつり」というのを開催しています。綾町では6カ所参加してくれているのですが、イタリアにならって、綾在住の陶芸家が造った焼酎用のグラス(ワイングラスのこともある)を、同じく綾在住の織物家が創ったバッグに入れ、それを首から(ポシェットのように)ぶら下げて、10時〜16時まで、食べて、飲んで、をやります。チケット代は6,000円ですが、かなり人気があります。初めた頃は参加団体がそれほど多くなかったのですが、今では道沿いに出店が出たり、綾のお箸やさんが創ったマイ箸が売れたりと、まちの産業が次から次へと発展していっています。綾町には長らく、観光協会というのはなかったのですが、そもそもこうした観光を扱う課は、産業観光課です。つまり、産業と観光を結びつけることが大切だという考えでしょう。その他のイベントとしては、「隣人まつり」というのをやっています。これは、ソトコトという雑誌がノウハウを持っているのですが、要は近くの人を集めて、パーティーしましょう、というものです。現在では綾町の人に限定して開催しているのですが、出席した方からは、「あら、あなたも綾なの?」という声が聴かれるくらいに、皆さん隣近所のことをご存知ないんです。というのも、綾町は県外から移住してきた方も多いからでしょうね。

(写真:とてもおしゃれなキッチン)
CCC 地域における活動をとても大切にされているんですね。
濱田 そうですね。こうした考えは、もともと綾町長であった合田町長の考えによるのではないかと思います。合田町長は、非常に(政治)哲学がしっかりされていて、住民というのは怠惰だから、ニーズに答えてはいけない。行政の長というのは、住民を導かなくてはならないのだ、というお考えで動いていらした。だからこそ、1988年に有機農業条例を制定されたり、自治公民館の合田方式(1つの区を250〜300戸にする方式で、その中から公民館長を選出、毎月1回公民館長会議を開く)を開発されたりしたのだろうと思います。またアメリカにならって、コミュニティスクールを開き、中学生に地域のことを考えるきっかけを与えるということもされていました。郷土愛を育てることが、人としての基本だと考えられていたのでしょう。
後編へ続く。。。
2010年01月20日
【取材】人間関係アプローチ宮崎きらきら 辰身信子さん(後編)
インタビュー前編はこちら

(写真:カウンセリングルームは穏やかな気持ちになれる)
■インタビュー後編■
CCC さて、今度は視点を変えて、経営的なことについて伺いたいのですが、きらきらさんではどのようにして収益を上げていらっしゃるのですか?
辰身 私たちの分野では、かつて行政から委託事業を受けるとはいっても、少額なものが多かったですし、助成金なども単発のものばかりで、あまりありませんでした。委託事業や助成金は、介護や子どもなどを対象としていて、私たちが対象とする人間関係やメンタルヘルスという人間としてもっとも必要なことにはあてはまりません。また、助成金をいただいたとしても、いただいた3年間はいいのですが、それ以降、2代目、3代目という継続性を考えたり、また、事業を行うのに精一杯で、疲れてしまっている方々を見てきました。ですから、私もNPOのことを学んでいたこともあり、自主運営できるNPOという形で立ち上げました。現在は、立ち上げた当時の売上の3倍ほどになっています。そして、年間売上の3割を事務費に、7割を講師に分配し、事務局や会計の方にもちゃんとお給料を支払っています。
私が心理学を学びはじめたころは、先輩が辞めないとその職には就けないよといわれていました。でもそうではなくて、資格を持った人がきちんと資格を活かした仕事に就け、それで食べていけるようになれればと思っています。そういう意味で、きちんとした料金制度をととのえ、食べていける仕組みを作ることができたことが良かったと思っています。
CCC NPOという法人形態よりも、合同会社等の仕組みでもよかったのではないでしょうか?
辰身 それはいろんな方にいわれます。でも、私としては、まず営利よりもミッションにこだわりたかったんです。まず、立ち上げるときに、「私こういうのやるけど、この指とまれ!」といったときに、2人の方が私の指にとまってくださいました。それぞれの方が「この人なら」という方を連れてこられて、7名ほどで法人のミッションである定款について話し合いました。実は定款を作るのに1年かかっているのですが、その1年の間にもいろいろやりとりがありましたし、そこで私たちがやることの意味等をしっかり考えました。その間に離れていってしまった方もいます。でも、そのことがミッションを共有するということにも繋がりました。ミッションを共有したメンバーは、現在までの6年間ずっと一緒に活動しています。
この他に、NPOとした理由について、行政とのつながりと地域のつながりを大切にしたいという気持ちもありました。行政とNPOが対等にしっかり手を取り合えば、地域のためになると思ったからです。
CCC なるほど。それでは時間も迫ってきましたので、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、現在の活動の障害になっていることはありますか?ということです。もう1つはこういった制度があったらいいなと思うことはありますか?という質問です。
辰身 順にお答えしますね。まず、現在の活動の障害になっていることは、昼間活動することができる方が少ないということです。実はカウンセラー・講師の募集をしているのですが、なかなか集まらないのが現状です。こちらも、プログラム等はかなりの数を開発しているので、ぜひ共感していただいて、一緒に働いてくださる方を募集しています。
次に、制度としてあったらいいなと思うことは3つあります。1つは、人権教育の中にメンタルヘルスを入れてほしいということです。メンタルヘルスは、人間の根幹の問題ですから、ぜひ人権教育として身近なところからメンタルヘルスを語ることができるようになったらいいなと思います。もう1つは、行政に携わる方々へのメンタルヘルスも考慮してほしいということです。実は,現在民間企業に対しては、メンタルヘルスに関する講師の派遣制度があるのですが、行政に対してはありません。ですから、行政の方々もメンタルヘルス講座を体験してほしいと思っています。そして最後に、行政とNPOの恊働といいますが、実際に行政の方々がNPOに出向できるような制度があったらいいなと思います。そうすると、市民の方々が何に困っているのか、ということがわかるようになりますし、そのための制度設計にも役立つと思います。また、NPOの現状を知っていただき、今後の恊働に活かしていけるのではないかと思います。
インタビュー終わり

(写真左 代表の辰身さん、右 井上)
***
誰もが愛されたい、信じてもらいたい、大切にされたいという基本的な欲求を持っているとおっしゃる辰身さん。だからこそ、自分で自分のきらきらに気づき、自分を変えていく場所が必要なんです、とおっしゃっていました。今の若い人たちについて、そういった言葉に耳を傾ける素直さがあるとおっしゃる辰身さん。だからこそ、今、大人の力量・スキルが問われているとおっしゃっていました。
貴重なお話、本当にありがとうございました。
今回は、ご都合がつかず、サミットにはご参加いただけないということでしたが、次回のサミットには、ぜひご参加いただきたいと思っています。その折にはどうぞよろしくお願いいたします。
最後に、お土産までいただきまして、ありがとうございました。
インタビュー 井上、三輪

(写真:カウンセリングルームは穏やかな気持ちになれる)
■インタビュー後編■
CCC さて、今度は視点を変えて、経営的なことについて伺いたいのですが、きらきらさんではどのようにして収益を上げていらっしゃるのですか?
辰身 私たちの分野では、かつて行政から委託事業を受けるとはいっても、少額なものが多かったですし、助成金なども単発のものばかりで、あまりありませんでした。委託事業や助成金は、介護や子どもなどを対象としていて、私たちが対象とする人間関係やメンタルヘルスという人間としてもっとも必要なことにはあてはまりません。また、助成金をいただいたとしても、いただいた3年間はいいのですが、それ以降、2代目、3代目という継続性を考えたり、また、事業を行うのに精一杯で、疲れてしまっている方々を見てきました。ですから、私もNPOのことを学んでいたこともあり、自主運営できるNPOという形で立ち上げました。現在は、立ち上げた当時の売上の3倍ほどになっています。そして、年間売上の3割を事務費に、7割を講師に分配し、事務局や会計の方にもちゃんとお給料を支払っています。
私が心理学を学びはじめたころは、先輩が辞めないとその職には就けないよといわれていました。でもそうではなくて、資格を持った人がきちんと資格を活かした仕事に就け、それで食べていけるようになれればと思っています。そういう意味で、きちんとした料金制度をととのえ、食べていける仕組みを作ることができたことが良かったと思っています。
CCC NPOという法人形態よりも、合同会社等の仕組みでもよかったのではないでしょうか?
辰身 それはいろんな方にいわれます。でも、私としては、まず営利よりもミッションにこだわりたかったんです。まず、立ち上げるときに、「私こういうのやるけど、この指とまれ!」といったときに、2人の方が私の指にとまってくださいました。それぞれの方が「この人なら」という方を連れてこられて、7名ほどで法人のミッションである定款について話し合いました。実は定款を作るのに1年かかっているのですが、その1年の間にもいろいろやりとりがありましたし、そこで私たちがやることの意味等をしっかり考えました。その間に離れていってしまった方もいます。でも、そのことがミッションを共有するということにも繋がりました。ミッションを共有したメンバーは、現在までの6年間ずっと一緒に活動しています。
この他に、NPOとした理由について、行政とのつながりと地域のつながりを大切にしたいという気持ちもありました。行政とNPOが対等にしっかり手を取り合えば、地域のためになると思ったからです。
CCC なるほど。それでは時間も迫ってきましたので、最後に2つお伺いしたいと思います。1つは、現在の活動の障害になっていることはありますか?ということです。もう1つはこういった制度があったらいいなと思うことはありますか?という質問です。
辰身 順にお答えしますね。まず、現在の活動の障害になっていることは、昼間活動することができる方が少ないということです。実はカウンセラー・講師の募集をしているのですが、なかなか集まらないのが現状です。こちらも、プログラム等はかなりの数を開発しているので、ぜひ共感していただいて、一緒に働いてくださる方を募集しています。
次に、制度としてあったらいいなと思うことは3つあります。1つは、人権教育の中にメンタルヘルスを入れてほしいということです。メンタルヘルスは、人間の根幹の問題ですから、ぜひ人権教育として身近なところからメンタルヘルスを語ることができるようになったらいいなと思います。もう1つは、行政に携わる方々へのメンタルヘルスも考慮してほしいということです。実は,現在民間企業に対しては、メンタルヘルスに関する講師の派遣制度があるのですが、行政に対してはありません。ですから、行政の方々もメンタルヘルス講座を体験してほしいと思っています。そして最後に、行政とNPOの恊働といいますが、実際に行政の方々がNPOに出向できるような制度があったらいいなと思います。そうすると、市民の方々が何に困っているのか、ということがわかるようになりますし、そのための制度設計にも役立つと思います。また、NPOの現状を知っていただき、今後の恊働に活かしていけるのではないかと思います。
インタビュー終わり

(写真左 代表の辰身さん、右 井上)
***
誰もが愛されたい、信じてもらいたい、大切にされたいという基本的な欲求を持っているとおっしゃる辰身さん。だからこそ、自分で自分のきらきらに気づき、自分を変えていく場所が必要なんです、とおっしゃっていました。今の若い人たちについて、そういった言葉に耳を傾ける素直さがあるとおっしゃる辰身さん。だからこそ、今、大人の力量・スキルが問われているとおっしゃっていました。
貴重なお話、本当にありがとうございました。
今回は、ご都合がつかず、サミットにはご参加いただけないということでしたが、次回のサミットには、ぜひご参加いただきたいと思っています。その折にはどうぞよろしくお願いいたします。
最後に、お土産までいただきまして、ありがとうございました。
インタビュー 井上、三輪
○基本情報
■団体名 人間関係アプローチ宮崎きらきら
■代表者名 辰身 信子
■所在地 宮崎市鶴島2−9−6 みやざきNPOハウス308号
■ホームページ http://www.kirakira.fromc.jp/index.html
○あわせて読みたい
■街が元気だネット「特集NPOレポート」http://www.machi-gennki.net/npo-report/kirakira/index.html
■辰身さんのブログ「NPOきらきら日記」http://kira2.miyachan.cc/
■みやざきNPO・ボランティア団体ライブ情報「ぶーら・ボーラ」http://www.bura-vola.org/vd/a020388/
■きらきら講師藤田さんのブログ「きらきらイメジェリー」http://blog.canpan.info/npo-kirakira/
2010年01月20日
【取材】人間関係アプローチ宮崎きらきら 辰身信子さん(前編)
インタビューにお応えいただいたのは、代表理事の辰身信子さん。
インタビューに応じていただく前に、「きらきらカフェ」を見せていただきました。
きらきらカフェは、辰身さんがこのNPOを立ち上げた当時からあり、気楽に立ち寄ることのできる場所、ゆっくりできる場所がまちなかに欲しいという気持ちから、作られたそうです。現在は、カフェのほか、講座も開催されているそうです。

(写真:きらきらカフェの様子)
*
インタビュー
CCC ホームページで活動内容について記載されていたのですが、より詳しく活動の内容と参加者、講座等の雰囲気について教えてください。
辰身 講座事業は、7つの講座があります。順に親業講座、看護/介護学講座、教師学講座、自己実現のための人間関係講座、エニアグラム講座、きらきらイメジェリー、メンタルヘルス講座です。
親業講座は、子どもとの関係を豊かにするために、専業主婦の方や育児休業中の方にいらしていただいています。年3回ほど講座を開き、毎回5〜6名の方にご参加いただいています。
看護/介護学講座は、看護や介護のお仕事に就かれている方を対象に、患者さん、利用者さんとの関係を豊かにするための講座を年1回開いています。これは10名ほどのご参加をいただいています。
教師学講座は、学校の先生を対象にした講座です。年2回、開催させていただきました。学校の先生は日頃、学校内での研修が多いので、なかなかご参加いただけないのですが、3〜4名の方のご参加をいただいています。今、教員のうつが増えているので、何とかストレス軽減へ向けてのお手伝いをしたいと思っているところです。
エニアグラム講座は、エニアグラムという手法を用いて、自分自身の性格の傾向を知り、どのように改善していけばよいのか、ということを古来の数の法則を用いて分析していくものです。若い方にも非常に好評をいただいています。以前、看護学校の学生さんのグループワークでエニアグラムを用いたのですが、日頃なかなかきっかけがつかめずコミュニケーションがとれていなかった人たちも、これでコミュニケーションがとれたり、眼がきらきら輝いたり、とてもうれしい変化を目の当たりにしたことがあります。
このほか、きらきらイメジェリーというのは、助産師さんが主に行っているもので、産前産後のうつを予防しようとするものです。現在、非常に好評をいただいているもので、つい先日も、この講座についてのお問い合わせがありました。年4回開催し、参加者は30名ほどです。
メンタルヘルス講座は、講演事業の方に吸収されている格好ですが、企業と契約をし、事業所内でメンタルヘルスについての講演をおこなったり、個別に依頼を受け、その依頼主に応じた講演、講座を行っています。
相談事業に関しては、こちらの事務所で行った相談については、年70〜80コマ程度あります。
講演事業は、企業契約のほか、保育所や学校、養護学校、PTA、行政、企業等のご依頼を受け、それぞれのニーズに合わせた講演を100回くらい行っています。
CCC それはすごいですね。そういった講演はお一人でされるんですか?
辰身 一人ではなく、当法人のスタッフで分担して行います。当法人の正会員がスタッフで、2名が事務局、2名が会計、6名が講演、講座の担当です。6名のうち、専業が3名、兼業が3名です。それぞれ、保健師やソーシャルワーカー、精神保健福祉師(PSW)等の資格をもっています。
CCC みなさん、専門性をもたれて活動をされているんですね。
辰身 100人いたら、100通りのプログラムが必要だというのが、私たちの考えです。専門性に基づいてプログラム開発を行っていくわけですが、プログラムは自分探しのお手伝いをするものです。自分探しをすると、受講された方の3分の1はよかった、3分の1は普通、3分の1の方は苦しくなります。その苦しくなった方に寄り添える方法も、私たちは知っています。そこまで責任を持ってフォローしてこそ、専門家がこうした活動をする由縁なのではないかと思います。
たとえば、エニアグラムのタイプを導きだすために私たちが用いている質問は、武田先生が開発されたものですが、108の質問があります。これは私たちの煩悩と同じです。その質問に答え、導きだされた数により、自分がどんな人だということがわかったとき、あなたは間違っていないんだよ、あなたの中に輝く原石のようなものがあるんだよ、でももっとこうすれば成長できるよ、ということまでやってこそ、専門家なのだろうと思います。
CCC 人の心は宇宙なんですね。(一同感心)
辰身 そうです。ただ、これが万能だと思っているわけではありません。でも、エニアグラムを体験してもらうことで、自分を発見でき、自分の成長の方向性が見えるわけですから、特に若い人に体験していただけるように、500円程度の実費負担で行うこともあります。

(写真:きらきらカフェにはたくさんの本がある)
【・・・後編に続く】
後編はこちら。
インタビューに応じていただく前に、「きらきらカフェ」を見せていただきました。
きらきらカフェは、辰身さんがこのNPOを立ち上げた当時からあり、気楽に立ち寄ることのできる場所、ゆっくりできる場所がまちなかに欲しいという気持ちから、作られたそうです。現在は、カフェのほか、講座も開催されているそうです。

(写真:きらきらカフェの様子)
*
インタビュー
CCC ホームページで活動内容について記載されていたのですが、より詳しく活動の内容と参加者、講座等の雰囲気について教えてください。
辰身 講座事業は、7つの講座があります。順に親業講座、看護/介護学講座、教師学講座、自己実現のための人間関係講座、エニアグラム講座、きらきらイメジェリー、メンタルヘルス講座です。
親業講座は、子どもとの関係を豊かにするために、専業主婦の方や育児休業中の方にいらしていただいています。年3回ほど講座を開き、毎回5〜6名の方にご参加いただいています。
看護/介護学講座は、看護や介護のお仕事に就かれている方を対象に、患者さん、利用者さんとの関係を豊かにするための講座を年1回開いています。これは10名ほどのご参加をいただいています。
教師学講座は、学校の先生を対象にした講座です。年2回、開催させていただきました。学校の先生は日頃、学校内での研修が多いので、なかなかご参加いただけないのですが、3〜4名の方のご参加をいただいています。今、教員のうつが増えているので、何とかストレス軽減へ向けてのお手伝いをしたいと思っているところです。
エニアグラム講座は、エニアグラムという手法を用いて、自分自身の性格の傾向を知り、どのように改善していけばよいのか、ということを古来の数の法則を用いて分析していくものです。若い方にも非常に好評をいただいています。以前、看護学校の学生さんのグループワークでエニアグラムを用いたのですが、日頃なかなかきっかけがつかめずコミュニケーションがとれていなかった人たちも、これでコミュニケーションがとれたり、眼がきらきら輝いたり、とてもうれしい変化を目の当たりにしたことがあります。
このほか、きらきらイメジェリーというのは、助産師さんが主に行っているもので、産前産後のうつを予防しようとするものです。現在、非常に好評をいただいているもので、つい先日も、この講座についてのお問い合わせがありました。年4回開催し、参加者は30名ほどです。
メンタルヘルス講座は、講演事業の方に吸収されている格好ですが、企業と契約をし、事業所内でメンタルヘルスについての講演をおこなったり、個別に依頼を受け、その依頼主に応じた講演、講座を行っています。
相談事業に関しては、こちらの事務所で行った相談については、年70〜80コマ程度あります。
講演事業は、企業契約のほか、保育所や学校、養護学校、PTA、行政、企業等のご依頼を受け、それぞれのニーズに合わせた講演を100回くらい行っています。
CCC それはすごいですね。そういった講演はお一人でされるんですか?
辰身 一人ではなく、当法人のスタッフで分担して行います。当法人の正会員がスタッフで、2名が事務局、2名が会計、6名が講演、講座の担当です。6名のうち、専業が3名、兼業が3名です。それぞれ、保健師やソーシャルワーカー、精神保健福祉師(PSW)等の資格をもっています。
CCC みなさん、専門性をもたれて活動をされているんですね。
辰身 100人いたら、100通りのプログラムが必要だというのが、私たちの考えです。専門性に基づいてプログラム開発を行っていくわけですが、プログラムは自分探しのお手伝いをするものです。自分探しをすると、受講された方の3分の1はよかった、3分の1は普通、3分の1の方は苦しくなります。その苦しくなった方に寄り添える方法も、私たちは知っています。そこまで責任を持ってフォローしてこそ、専門家がこうした活動をする由縁なのではないかと思います。
たとえば、エニアグラムのタイプを導きだすために私たちが用いている質問は、武田先生が開発されたものですが、108の質問があります。これは私たちの煩悩と同じです。その質問に答え、導きだされた数により、自分がどんな人だということがわかったとき、あなたは間違っていないんだよ、あなたの中に輝く原石のようなものがあるんだよ、でももっとこうすれば成長できるよ、ということまでやってこそ、専門家なのだろうと思います。
CCC 人の心は宇宙なんですね。(一同感心)
辰身 そうです。ただ、これが万能だと思っているわけではありません。でも、エニアグラムを体験してもらうことで、自分を発見でき、自分の成長の方向性が見えるわけですから、特に若い人に体験していただけるように、500円程度の実費負担で行うこともあります。

(写真:きらきらカフェにはたくさんの本がある)
【・・・後編に続く】
後編はこちら。











